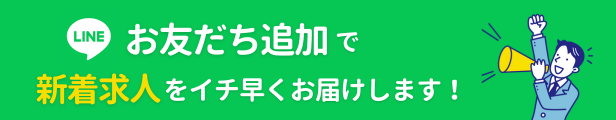「パンの製法」と一言で言っても、その製法は「ストレート法」「中種法」「ポーリシュ法」、「自家製酵母」など、細かく分けると20種類ほどあります。
それぞれに特徴があるため、それをどのように使い分け、活用するかはブーランジェ次第。
今回は代表的なストレート法と中種法の2つの製法について、その特徴をご紹介します。
ストレート法
ストレート法は特殊な配合を除き、全材料を一度にミキシングして生地を作る製法です。
ホームベーカリーでも採用されている製法のため、比較的簡単な製法と言えるでしょう。
特徴としては以下のような点が挙げられます。
利点
・風味が良い
・発酵時間が短い
・作業スペースが少なくて済む
欠点
・できあがったパンのボリューム感が出にくい
・老化が早い(日持ちしない)
生地を作るための仕込みが1回で済み、作業内容自体が比較的簡単なことが特徴。
発酵時間も短く、仕込みから焼き上げまでの総時間は、一般的な食パンの配合で約4時間15分です。
ただし、製法がシンプルな分、生地の修正が難しく、生地の良し悪しがそのままパンに出るので、仕込み工程の際は特に気を付ける必要があります。
このような特徴から、大量生産よりも仕込量の少ない製品にストレート法を採用するのが良いとされています。
中種法
中種法は、使用する小麦粉の一部をイースト、水、時には副材料も加えて中種を作り、2時間以上発酵をとった後、残りの材料を加えて本捏ねをし、生地を作る製法です。
中種法でつくるパンには、以下のような特徴があります。
利点
・ボリュームがあり、ソフトな食感
・老化が遅い(日持ちする)
欠点
・中種法のための設備と作業スペースが必要
・所要時間が長い
・風味が物足りない
中種を作ってから本捏ねする手間がかかりますが、手順さえ守れば生地の質が一定になりやすく、また修正もしやすいので、出来上がりの製品が安定しやすいという特徴があります。
中種法で食パンを製造する場合の総時間は、ストレート法の1.5倍の約6時間30分。
発酵の時間が長いため、焼き立てパンを売りにしているような店ではあまり採用されませんが、逆に「日持ち」を重要視する大手の製パン工場などではよく用いられる製法です。
どちらの製法も利点と欠点がありますが、それぞれの特徴を生かしながら併用しているお店も多くあります。
例えば1日に2回カンパーニュをつくる際、1回目はストレート法で、2回目は中種法で仕込むことも。
理由は、朝から来てくださるお客様のために早く焼き上げたいから、1回目は時間短縮を重視したストレート法を採用。
2回目は時間の制限がないため、パンのボリュームや老化の遅さなどを重視して中種法を採用、などで使い分けるのです。
このように、たとえ同じパンでも、求められるものや状況に応じて製法を変えて作ることも多くあります。
今回紹介したもの以外にも、パンづくりには多くの製法があります。
お客さまはどんなパンを求めいているのか、ニーズを考えながらいろいろな製法についての理解を深めることで、パン職人としての技術力が高まるのではないでしょうか。