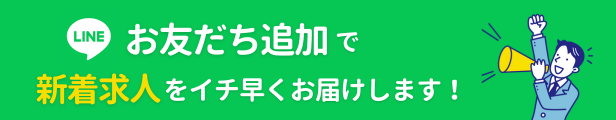パティスリーをはじめとする洋菓子・パン業界にとって、深刻な問題となるのがバター不足。
品薄になると必要な量の確保が難しくなるだけでなく、価格が高騰するため経費にも影響し、経営を圧迫する一因にもなります。
では、なぜバターは度々足りなくなるのでしょうか。
物価上昇や猛暑の影響による生産量減少など、様々な要因がありますが、今回はその背景をまとめてみました。
■バター不足はこうして起こる
バターが足りなくなる背景には、バターの原料である生乳そのものが不足しているという事実があります。
牛乳・生クリームなどの乳製品の中で、バター用となる生乳の割合は最も低く、生乳の生産が減るとその影響を一番に受けてしまいます。
賞味期限が短く、需要がより高い、飲用の牛乳などに生乳を多く振り分けた結果、加工品であるバターを製造するための生乳が足りなくなってしまうのです。
生乳の2014年の国内生産量は6.2万トンとなっており、1990年以降で最低基準の数字です。
また、酪農家にとって、円安による光熱費や飼料価格の上昇は悩みの種となっており、経営を続けることの難しさから、農家の減少や規模の縮小につながり、さらに国内生産量が減っているのが現状です。
■輸入バターの複雑な仕組み
バターは国内産だけではなく、海外からも大量に輸入しています。
「輸入しているなら足りるのでは?」と考えてしまいますが、国の政策によってバターには高い関税がかけられ、輸入量が制限されているため、需要に対して十分な量を輸入できていないのが現状です。
安価な輸入品が大量に流通することによる、国産乳製品の価格の下落を避けるための保護措置とされていますが、輸入量の調整は非常にデリケートな問題です。
市場や消費の動向を見た上で慎重に輸入量を判断するため、気候などの影響による急な国内産のバター不足の動きに、追いつけていないのが実情となっています。
■今後もバターは足りない?
繰り返されるバター不足ですが、供給が安定するためには政府の柔軟な輸入施策や、円安対応、酪農家への補助などが課題になります。
農水省は2015年のバター輸入について、品薄のため1万トンの追加輸入を決定しましたが、根本的な問題解決にはなっていません。
そのため、パティスリーにとって忙しくなり始める秋や繁忙期のクリスマスシーズン前には、品薄と値上がりを念頭に置いた仕入と原価管理が必要と言えそうです。