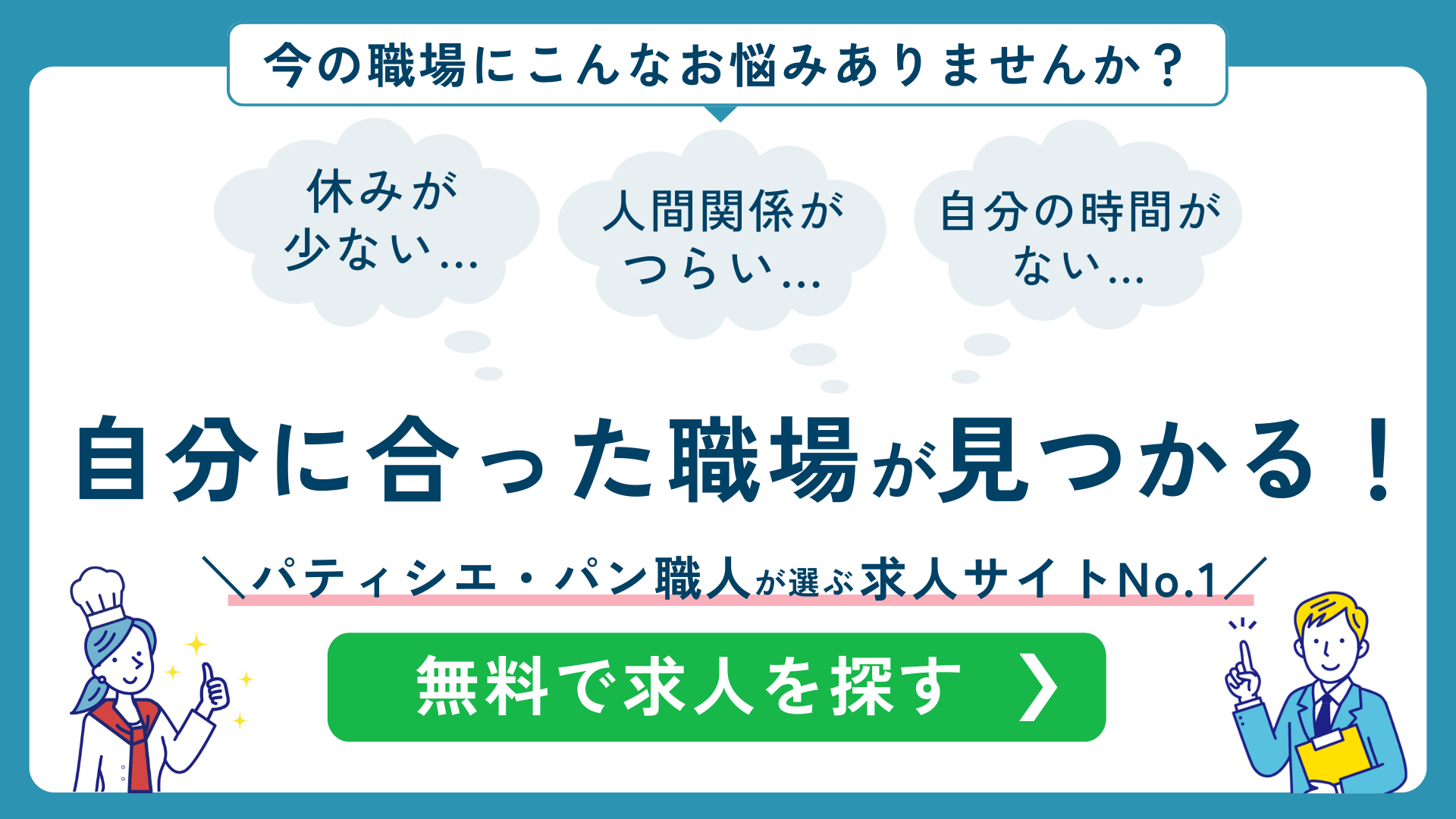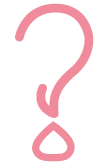
植物性自然毒
カテゴリ:食中毒

もしも、食中毒が疑われる場合は、医療機関に受診し、その際食べた植物があれば持参するようにする。
原因食品と症状については以下の通りである。
ジャガイモ
芽や光に当たって緑色になっている部分や未熟なジャガイモに含まれるソラニン、チャコニンが毒素化する。加熱しても分解されないので、完全に取り除く必要がある。症状は腹痛、下痢、頭痛、嘔吐、めまい、呼吸困難など。
スイセン
リコリン等が含まれ有毒。葉が食用のニラ、ノビルに似ているので注意が必要。症状は吐き気、嘔吐、下痢、よだれ、発汗、頭痛、昏睡症状など。
アジサイ
アジサイの葉に含まれる。添え物として使われていても、決して口にしてはいけない。症状は嘔吐、めまいなど。
トリカブト
アコニチン等が含まれ有毒。食用のニリンソウなどに似ているので注意が必要。症状は嘔吐、下痢、手足の麻痺。重症の場合は死に至る。
ハシリドコロ
ヒヨスチアミンなどが含まれ有毒。食用のフキノトウなどに似ている。症状は幻覚、下痢、嘔吐、血便、めまいなど。
このほかにも、青梅(アミグダリン)、アマチャ、イヌサフラン、カロライナジャスミン、グロリオサ、クワズイモ、ジギタリス、シャクナゲ、スノーフレーク、タマスダレ、チョウセンアサガオ、テンナンショウ類、ドクゼリ、ドクニンジン、バイケイソウ、ヒメザゼンソウ、ベニバナインゲン、ユウガオ、ヨウシャヤマゴボウなど
毒キノコ
毒キノコと食用キノコは類似しているものが多く、素人では判別するのが難しい。猛毒のキノコは摂取してから数時間で死に至るものもある。
予防方法
種類が判別できない植物は採らない、食べない、人に食べさせない。専門家の確認を行う。
家庭などで育てる時には、観賞用と一緒に栽培しない。
更新日:2019年07月30日
作成日:2018年09月13日
更新日:2019年07月30日
作成日:2018年09月13日
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの協力のもと制作されています。
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの
協力のもと制作されています。
関係項目
• 動物性自然毒
動物がもともと保有している、または食物連鎖を通して動物の体内に取り込まれる有毒成分。フグや貝類などの魚介類由来によるものが多い。重症化、また死に至る場合もあり食品衛生上特に重要視されるものである。 フグによる症状 中でも、フグにはテトロドトキシンという神経毒があり、喫食した場合、しびれや麻痺が現れはじめ重症の場合は死に至る事がある。フグ毒は肝臓、卵巣、皮など、種類により異なり、加熱調理しても壊れない。 一般の人がフグを調理、喫食することは極めて危険なため、販売されているアジなどの小魚のパック詰めに混入していないか確認が必要。飲食店であれば講習会を受講し、かつ保健所への届け出が必要となる。 貝による症状 貝毒では、消化器系、神経系の中毒症状があり、下痢や麻痺、口内の灼熱感、運動失調の症状を起こす事もある。最悪の場合、死に至る事もある。毒性を持つプランクトンは4~5月にかけて発生し、貝が蓄積することにより食中毒症状が発症する。そのため、水産担当局は冬の終わりから貝やプランクトンの検査を行っている。 その他、毒カマス等
• 腸炎ビブリオ
腸炎ビブリオとは、食中毒を引き起こす菌の一種である。 原因 ほとんどの原因食品が、加熱していない魚介(寿司や刺身)。生魚に触った手やまな板から他の食品につく事がある。菌は3%食塩濃度で最も活発化し、主に海水に生息している。海で感染された魚介類を経由して人体に入ることがある。また海水温度の上がる夏場に多く、4℃以下ではほとんど増殖はしなくなる。近年では、冷蔵、保冷での運搬技術の向上から、発症件数は減少傾向にある。 症状 潜伏期間は原因食品を食べてから、8〜24時間(平均約12時間)。激しい腹痛、下痢が主な症状で、まれに血便が見られる。発熱(37〜38℃)やおう吐を起こす場合もある。症状が現れてから1〜2日程度で回復するが、高齢者の中には死に至ったケースも報告されている。 予防方法 原因食材を4℃以下で保存すること、調理前に真水や酢で十分に洗うこと、調理器具や手指の洗浄などが重要である。また十分な加熱調理によってほとんどの菌が死滅する。