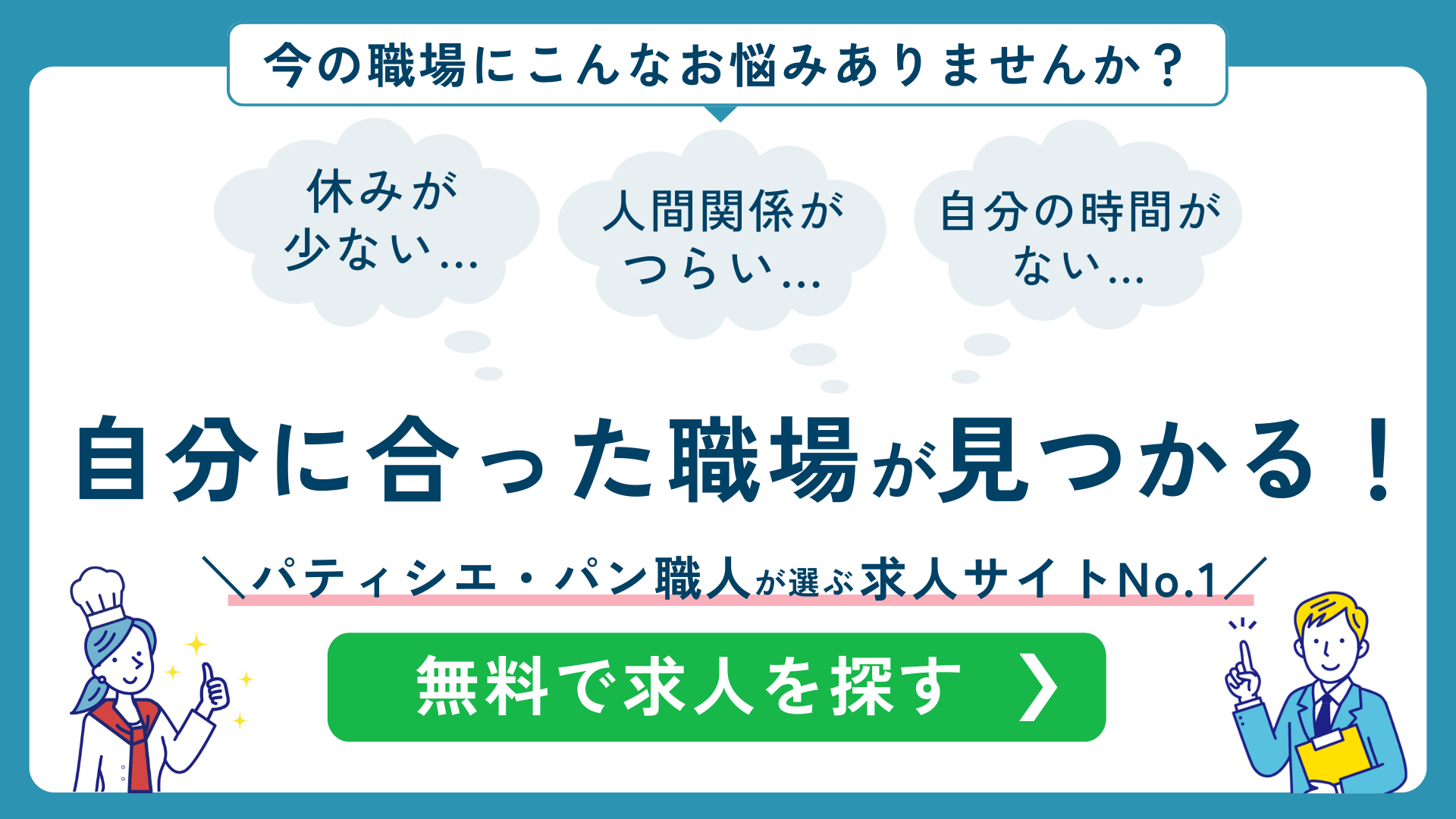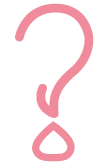
腸炎ビブリオ
カテゴリ:食中毒

原因
ほとんどの原因食品が、加熱していない魚介(寿司や刺身)。生魚に触った手やまな板から他の食品につく事がある。菌は3%食塩濃度で最も活発化し、主に海水に生息している。海で感染された魚介類を経由して人体に入ることがある。また海水温度の上がる夏場に多く、4℃以下ではほとんど増殖はしなくなる。近年では、冷蔵、保冷での運搬技術の向上から、発症件数は減少傾向にある。症状
潜伏期間は原因食品を食べてから、8〜24時間(平均約12時間)。激しい腹痛、下痢が主な症状で、まれに血便が見られる。発熱(37〜38℃)やおう吐を起こす場合もある。症状が現れてから1〜2日程度で回復するが、高齢者の中には死に至ったケースも報告されている。予防方法
原因食材を4℃以下で保存すること、調理前に真水や酢で十分に洗うこと、調理器具や手指の洗浄などが重要である。また十分な加熱調理によってほとんどの菌が死滅する。更新日:2019年07月30日
作成日:2018年09月13日
更新日:2019年07月30日
作成日:2018年09月13日
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの協力のもと制作されています。
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの
協力のもと制作されています。
関係項目
• ウェルシュ菌
ウェルシュ菌とは感染型食中毒を引き起こす菌のこと。 原因 酸素のないところを好む細菌、人や動物の腸内、下水等、広く生息する。主な原因となるのが、室温に長時間おいている食品に発生するもの。特に食肉が汚染されている場合が多く、これは食肉に含まれるグルタチオンなどの還元物質によるものだと報告されている。大量調理の食品中で増殖しやすく、また熱抵抗力があるのが特徴であり、加熱しても死滅しない。スープ、カレーなどの煮込み料理を加熱後に室温においておく事で細菌が増殖する。再加熱しても、死滅せず条件によっては発育を促す場合もあり、注意が必要。 症状 潜伏期間は細菌を摂取してから、6~18時間。24時間を経過してから発症することはほとんどみられない。主な症状は下痢、腹痛など。嘔吐、発熱はまれに発症するが、一般的には軽い症状で重症化することはない。 予防方法 重要な点は、菌の増殖を防ぐことである。調理した食品は食べ切るか、室温に長時間置いておかずに急いで冷蔵庫で保存する。
• ボツリヌス菌
ボツリヌス菌とは、ボツリヌス食中毒の原因となる細菌。 非常に強い毒性があり、ボツリヌス菌が検出されたら食品衛生法により、届出が義務づけられている。 原因 自然界(土壌、河川、動物の腸内)に広く存在し、加熱に強く、酸素のない状態を好む。真空パック食品、缶詰、瓶詰め、発酵食品(飯寿司など)、酸素が少ない状態のものが原因食品となる。強い神経毒を生み出す危険な菌である。人との食中毒との関係が強いのは、A・B・E、まれにFの4型。また1歳未満の乳児に対してはハチミツが原因食品となるが、ハチミツの中で菌が繁殖することはなく、乳児の腸内環境によって繁殖し、毒素を生み出すので特に注意が必要。 症状 潜伏期間は、原因食品を摂取してから8~48時間。多くは16時間を過ぎてから症状が現れる。初期症状は便秘(下痢、おう吐の場合もある)。その後、まぶたが垂れ下がる、物が霞んで見える、ろれつが回らなくなるなどの神経異常。発熱は少ないが、さらに症状が進行すると筋肉に麻痺を引き起こし、呼吸に関連する筋肉への影響も見られ、呼吸困難になることもある。 予防方法 ボツリヌス菌は増殖する際にガスを発生するので、容器が膨張している真空パック、缶詰、瓶詰めなどを摂取しない。 (真空パックしていても保存方法を確認し、常温で保存可能かを確認する) 食べる直前に加熱する。 1歳未満の乳児にははちみつを与えない。