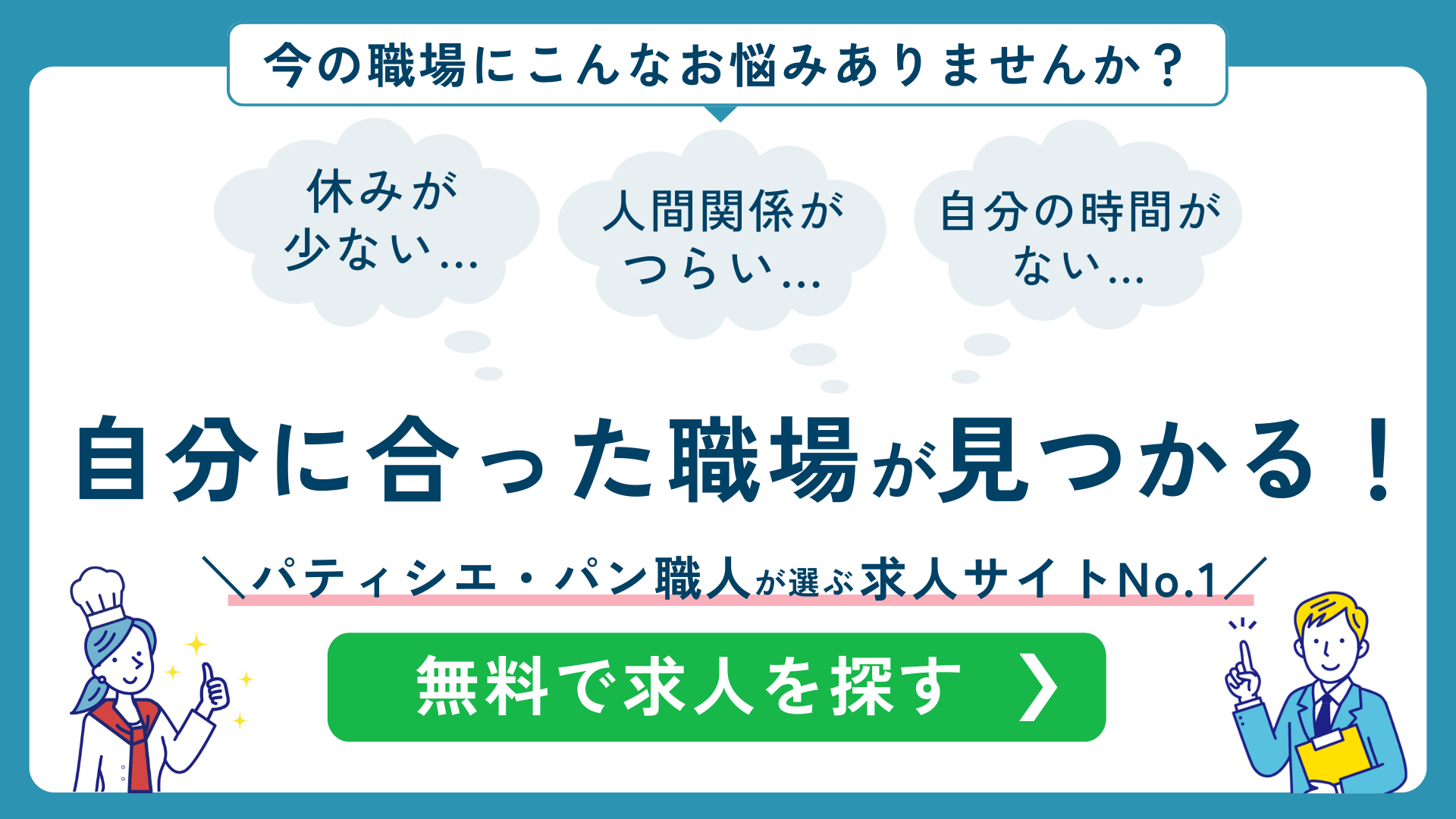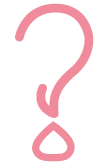
ウェルシュ菌
カテゴリ:食中毒

原因
酸素のないところを好む細菌、人や動物の腸内、下水等、広く生息する。主な原因となるのが、室温に長時間おいている食品に発生するもの。特に食肉が汚染されている場合が多く、これは食肉に含まれるグルタチオンなどの還元物質によるものだと報告されている。大量調理の食品中で増殖しやすく、また熱抵抗力があるのが特徴であり、加熱しても死滅しない。スープ、カレーなどの煮込み料理を加熱後に室温においておく事で細菌が増殖する。再加熱しても、死滅せず条件によっては発育を促す場合もあり、注意が必要。症状
潜伏期間は細菌を摂取してから、6~18時間。24時間を経過してから発症することはほとんどみられない。主な症状は下痢、腹痛など。嘔吐、発熱はまれに発症するが、一般的には軽い症状で重症化することはない。予防方法
重要な点は、菌の増殖を防ぐことである。調理した食品は食べ切るか、室温に長時間置いておかずに急いで冷蔵庫で保存する。更新日:2019年07月30日
作成日:2018年09月13日
更新日:2019年07月30日
作成日:2018年09月13日
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの協力のもと制作されています。
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの
協力のもと制作されています。
関係項目
• 肝炎ウイルス
肝炎ウイルスは、一般的にはA型・B型・C型・E型、まれにD型と大きく5種類に分類される。いずれも感染経路が異なるが、肝臓の細胞に影響を与え「急性肝炎」を引き起こす原因となる。 A型 ウイルスに汚染された食品や水を摂取することにより感染する。酸やアルコールへの耐性が強く、体内に入って不活化されることがない。 症状 潜伏期間は14~45日程度。38.4℃以上の発熱が3〜4日続く。また全身の倦怠感、吐き気やおう吐など。皮膚が黄色がかる「黄疸」といった症状も特徴。免疫のない中高年層は重症化することがあるが、慢性化することは少ない。 予防方法 衛生環境の改善、手洗いの徹底、生水の摂取をしない、予防ワクチン摂取、免疫グロブリンなど B型 血液・精液・唾液などにより感染する。輸血や注射針の共有といった医療事故で感染してしまうケースも報告されている。性行為感染、母子感染も起こりうる。 症状 潜伏期間は6週間~6か月。緩やかに発熱が起こり、倦怠感やおう吐など。重症を除いて1ヶ月程度で回復する。キャリア(無症状のまま病原体を保有する状態にある人)の90%は発症しないが10%は慢性肝炎、肝硬変、肝臓がんへと進行する。 予防方法 感染経路での配慮(医療時の衛生管理、コンドームの使用など)、ワクチンの摂取 C型 C型肝炎の原因となる。感染経路のほとんどが血液。慢性化することが多く、10年経過すると肝硬変、肝臓がんを発症させることがあり重要な病原ウイルスのひとつである。 症状 潜伏期間は(輸血後)2週間~16週間。発熱はなく全身倦怠感から症状が現れるものの、比較的症状は軽く気づかず慢性化することもある。徐々に食欲不振、おう吐、上腹部膨満感、濃色尿などが見られるようになる。これらに続いて黄疸が認められる例もある。 予防方法 ワクチンは研究中、治療は対症療法などがある。予防としては感染経路の遮断。 E型 E型肝炎の原因となるウイルス。ヒマラヤ山麓、亜熱帯地方の風土病として発展途上国での発症が報告されており、先進国では輸入感染と考えられている。近年は日本でも野生シカの生食が原因で感染した患者の報告がある。 症状 潜伏期間は14~45日間。急激に強い黄疸が出現し、12〜15日間続く。慢性化はしないが、妊婦の場合は致死率20%にも達すると言われている。 予防方法 対症療法のみ。予防方法としては発展途上国での飲食に留意すること。
• 動物性自然毒
動物がもともと保有している、または食物連鎖を通して動物の体内に取り込まれる有毒成分。フグや貝類などの魚介類由来によるものが多い。重症化、また死に至る場合もあり食品衛生上特に重要視されるものである。 フグによる症状 中でも、フグにはテトロドトキシンという神経毒があり、喫食した場合、しびれや麻痺が現れはじめ重症の場合は死に至る事がある。フグ毒は肝臓、卵巣、皮など、種類により異なり、加熱調理しても壊れない。 一般の人がフグを調理、喫食することは極めて危険なため、販売されているアジなどの小魚のパック詰めに混入していないか確認が必要。飲食店であれば講習会を受講し、かつ保健所への届け出が必要となる。 貝による症状 貝毒では、消化器系、神経系の中毒症状があり、下痢や麻痺、口内の灼熱感、運動失調の症状を起こす事もある。最悪の場合、死に至る事もある。毒性を持つプランクトンは4~5月にかけて発生し、貝が蓄積することにより食中毒症状が発症する。そのため、水産担当局は冬の終わりから貝やプランクトンの検査を行っている。 その他、毒カマス等