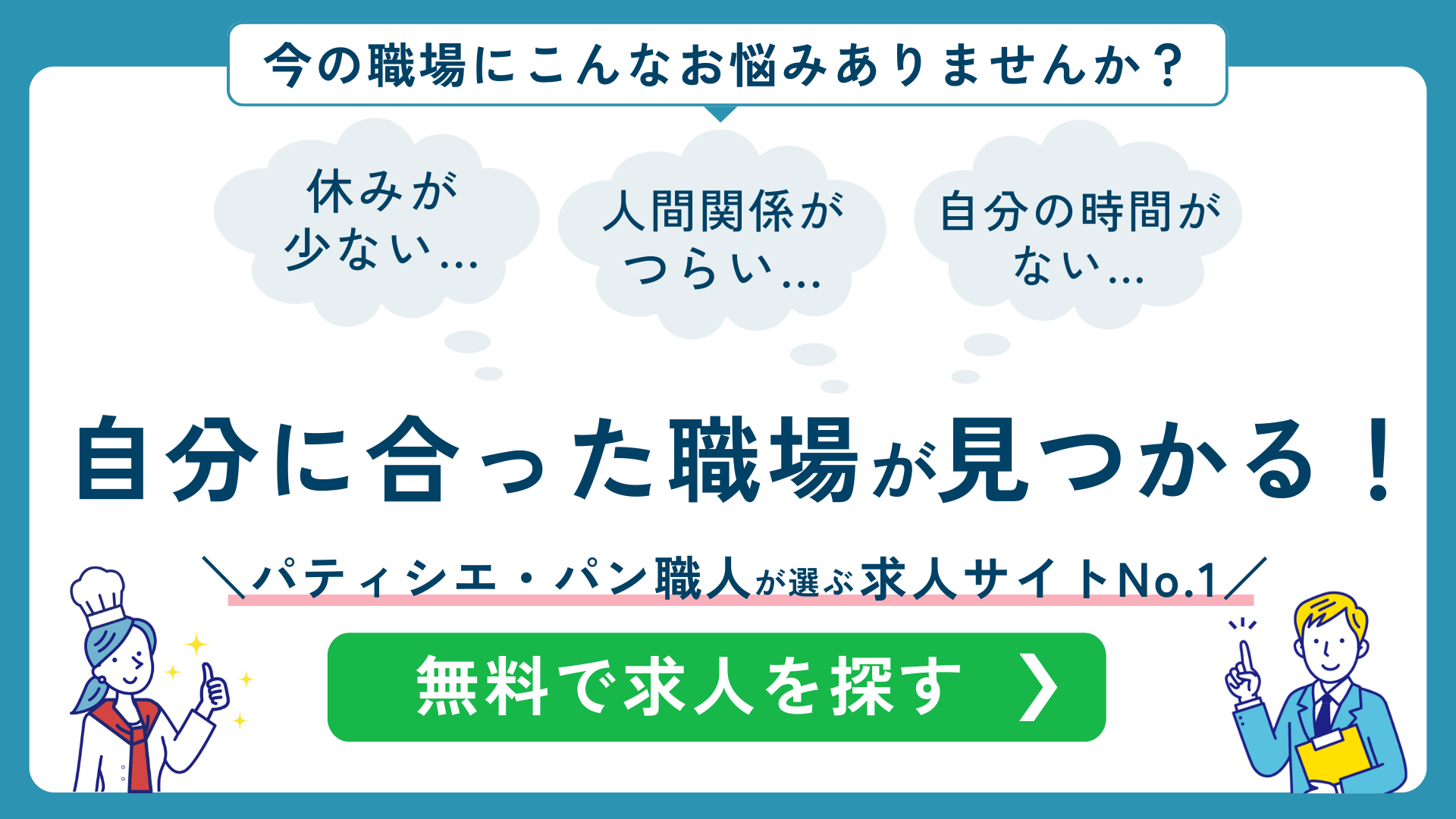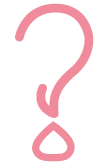
クレープ
カテゴリ:デザート

小麦粉に乳製品や糖類、鶏卵などを合わせた流動性のある生地をごく薄く焼いたもの。焼いた時にできるちりめん状の模様からクレープ(絹の意味)と呼ばれるようになった。
日本では生クリームやフルーツ等を巻いて食べたり、クレープシュゼット(仏:Crêpe Suzette)など、レストランデザートとして親しまれている。
歴史
フランスのブルターニュ地方のガレット(仏:galette)と呼ばれるそば粉で作った食べものがはじまりとされている。ブルターニュ地方は、かつては土地が痩せていて小麦が育ちにくかった為、そばが多く育てられていた。
17世紀フランス国王の妻アンヌ王妃がブルターニュ地方を訪れた際に、ガレットをとても気に入って宮廷料理に取り入れ、19世紀頃にはそば粉が小麦粉に変わり今のクレープと呼ばれるものが広がっていった。
日本には1970年代後半にフランスから伝わったとされ、1976年に渋谷公園通りの駐車場にて小さなワゴン車で販売されたのが初めとされている。
更新日:2018年12月11日
作成日:2018年09月12日
更新日:2018年12月11日
作成日:2018年09月12日
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの協力のもと制作されています。
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの
協力のもと制作されています。
関係項目
• タルト・ブルダルー
タルト・ブルダルー【仏:Tarte Bourdaloue】 タルト・ブルダルーとは、生地にアーモンドクリームを流し込み、その上に果物を乗せて焼いたタルトである。 特に洋梨を使用したタルト・ブルダルーは、Tarte aux poires Bourdaloue(タルト・オー・ポワール・ブルダルー)と呼ばれる。poires(ポワール)とは、フランス語で「洋梨」を意味する。 一般的に、ブルダルーはアーモンドのクリームの上に果物を乗せ、表面に砕いたマカロンと溶かしバターをかけて焼き色を付けたものである。 これをタルト生地の上に作ると、タルト・ブルダルーとなる。 歴史と由来 「ブルダルー」という名前の由来には次の2つ説がある。 1. 19世紀末~20世紀初頭のパリが繁栄していたベル・エポックの時代に、ブルダルー通りにあった菓子店で売られていたからという説。 Faquelle(ファスケル)、またはLesserteur(レセトゥール)という名のパティシエが考案したといわれている。 2. 長い説教で有名であったイエズス会の説教師Louis Bourdaloue(ルイ・ブルダルー)にちなんで命名されたという説。 彼はブルダルー通りに面した教会で説教を行っていた。 ルイ・ブルダルーは1704年没であるため、タルト・ブルダルーの由来である2つの説には約200年の開きがある。
• ガレット・ドラーンジュ
ガレット・ドラーンジュ【仏:Galette Dorānju】 ガレット・ドラーンジュとはパート・サブレを型を使わずに手で成形して作る、オレンジのタルト風菓子を指す。 土台の生地の外周に棒状にした生地で壁を作り、手でつまむように成形し、中にオレンジマーマレード・オレンジピール・アパレイユを敷いて焼き上げる。 「ドラーンジュ」はフランス語で「オレンジ」の意味であるため、ガレット・ドラーンジュは「オレンジのガレット」と呼ばれることもある。 ガレット・ドラーンジュに用いるパート・サブレは糖分より脂肪分(バター)の割合が多いタルト生地である。 そのため、歯ざわりが軽く、口の中でほろほろと崩れる脆さが特徴にあげられる。 ガレットの種類 『ガレット』と聞けば、クレープの原型であるそば粉の生地を焼き、卵や野菜を包んで正方形に折りたたんだ料理を想定する方もいるだろう。 しかし、ガレットは本来『円形に平たく焼いたもの』という意味であるため、料理と菓子の両方で使われる言葉である。 『ガレット』の名がつく菓子として、ガレット・ドラーンジュのほか、 ガレット・デ・ロワ 、 ガレット・ブルタルー がある。 歴史 ガレット・ドラーンジュの土台に用いるパート・サブレの、「サブレ」の名前の由来には次の3つの説がある。 1. サブレが作られたのが、フランスのサブレ=シュル=サルトであるからという説 2. 17世紀、サロンを開いていたサブレ公爵夫人が、バターをたっぷり使ったガトーセックを出したことが始まりであるからという説 3. フランス語で「Sable(サーブル)」は砂を意味し、砂が崩れるような食感から名づけられたという説 また、ビスケット生地やパイ生地で作った器に詰め物をした菓子や料理の総称が「タルト」であり、ガレット・ドラーンジュもタルトの一種である。 タルトは、誕生から長い期間、手で食事をしていた人類が、はちみつやクリームといった液状のものを食べられる器に入れることで食べやすくするという発想から生まれた。 この発想は古代ギリシャ、古代エジプト時代には既にあったともいわれるほど、長い歴史を持つものである。