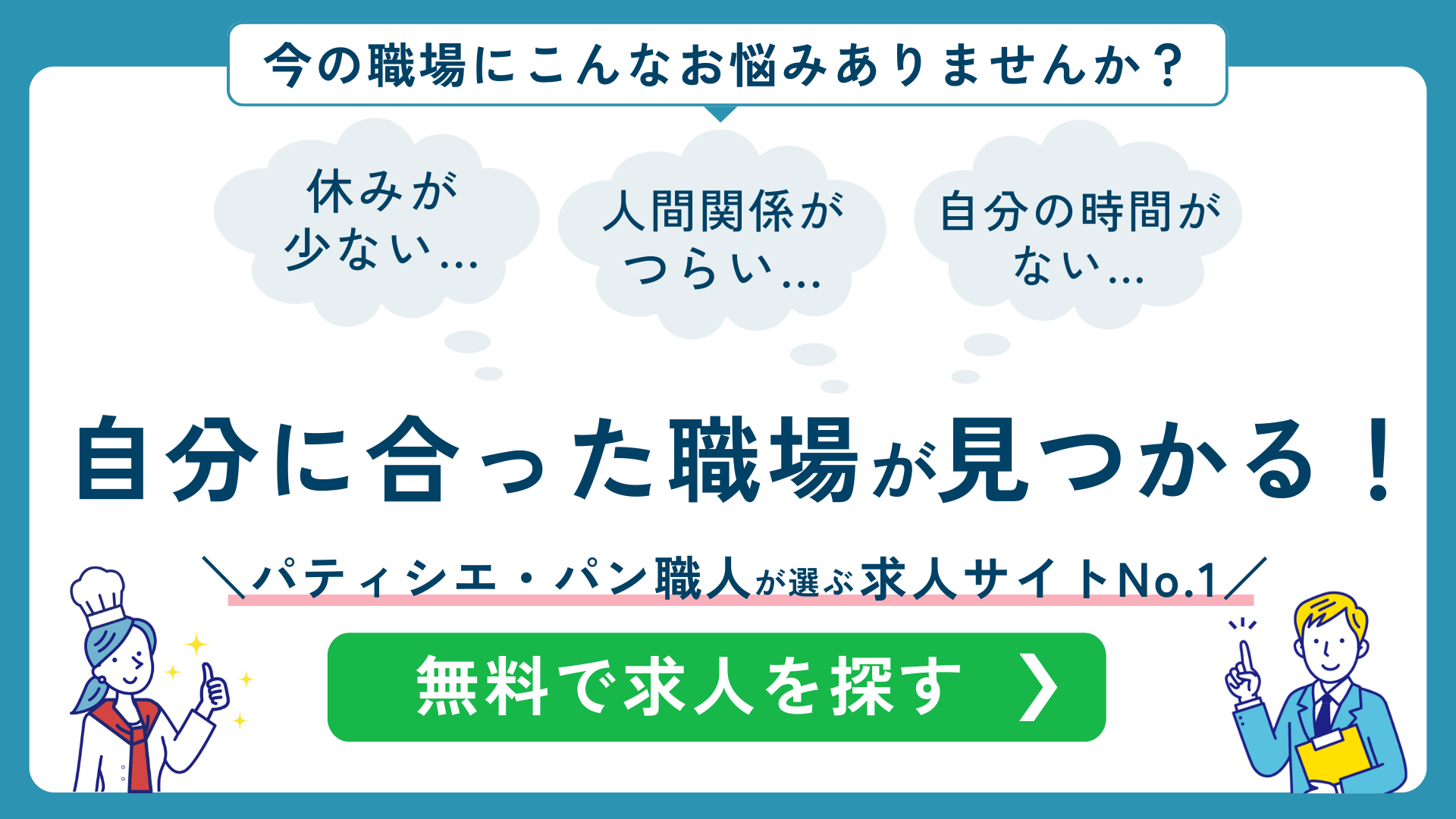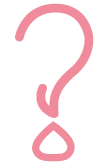
りんご
カテゴリ:果物類

バラ科リンゴ属の落葉高木樹。原産地は中央アジアや小アジアなど、諸説が存在する。
先史時代にはヨーロッパに自生していたと考えられ、現在では世界で最も栽培量の多い果実。
古代から世界中で知られ、早くから多くの品種があったとされている。
日本では明治時代から栽培が始まった。
晩春に白または薄紅の5弁花が開花し、早い品種は8月頃から、遅いものは4月頃まで収穫されるが、多くの品種が秋から冬に最も出荷される。
果実の直径は約3センチから15センチ。外皮は赤、黄緑または黄色をしている。
果肉は淡黄色または白色だが、外皮近くなど果肉が赤肉系になる品種もある。
大部分が食用に適し、甘味を中心に程よい酸味が調和して、口当たりやわらかい肉質を持つ。
外皮の色が良くついたものほど甘味が強く、味も濃い。
ただし、青りんごは緑色が強いほど熟度がすすんでいない。重みがあり、軽く指で弾くとはずんだ音がするものが新鮮とされている。
りんごのワックス
りんごの表面は時折油っぽくベタついていることがあるが、これはワックスや農薬ではなく、りんごから生成されるもの。果実が熟すことにより作られたリノール酸やオレイン酸などの不飽和脂肪酸が表皮に含まれるろう物質を溶かし、ワックスのような膜ができるのだ。りんごの扱い
りんごが最も嫌うのが温度差であり、特に熟成を進める物質であるエチレンガスを発生させるため、一緒に置くと熟成が早まってしまう。そのため、ひとつずつ新聞紙で包んでビニールに入れ、冷蔵庫に入れ保存するのがよいとされている。
また切った断面をそのままにすると、りんごに含まれるポリフェノールが酸化し、表面が茶色く変色してしまう。(褐変)
りんごを加熱調理しない場合には、食塩水やはちみつを溶かした水、酸化防止剤などに30秒程浸すことで、変色を防止することができる。
→りんごの品種
更新日:2018年12月11日
作成日:2018年09月07日
更新日:2018年12月11日
作成日:2018年09月07日
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの協力のもと制作されています。
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの
協力のもと制作されています。
関係項目
• りんごの品種
ふじ ふじは「国光」と「デリシャス」の交配種で、日本で最もたくさん作られているりんごの品種でもある。海外でも作られているりんごとして有名で、世界中で最も生産数の多い品種でもある。 ふじの主な生産地は青森県で、国内で生産されているふじ全体の約半分を占めている。 特徴 大きさは300~400gで、ソフトボールぐらいの大きさである。果汁は豊富で歯ざわりが良く、シャキシャキとした果肉は蜜が多いものも多く、甘味のバランスが比較的いい。糖度が高いものは高級品として扱われている。熟しすぎたものや古いものは煮崩れがしやすいので、果皮の艶のあるもの、張りのあるものを選ぶと良い。 貯蔵性が高く、保存は低温庫で半年以上持つと言われている。りんごの表面にワックス成分という白っぽいものが着いているが、これはりんごが保存性を高めるために自ら分泌しているものなので、落とさないようにして保存すると良い。ふじは多く出回っているため、価格も比較的安定している。 紅玉 紅玉の主な生産地は青森県で、9、10月頃から春先まで市場に出回る。ちょうど10月~11月頃が旬になる。 特徴 紅玉の大きさは200gぐらいの大きさで、他のりんごよりも小ぶり。真っ赤な果皮が特徴である。果肉はしまりがあるため、煮込んでも崩れにくく、扱いやすい。甘味もあるが酸味もしっかりあり、香りが豊かである。そのため、タルトタタンやアップルパイを作るのに適している。 紅玉はもとはアメリカ原産のりんごで、日本には明治時代始め頃から作られるようになった品種である。以前は多く出回っていたが、新品種に押されて数量が減少した時期もあった。だが、紅玉特有の酸味が菓子に向いていると見直され、生産量は回復してきた。生産量が増えたことにより、価格も手頃となった。見分け方としてはワックス成分の分泌が多いものが十分に熟しているといえる。 ジョナゴールド ジョナゴールドは「ゴールデン」と「紅玉」の交配種で、比較的多く作られているため、りんごの中でも身近な存在として知られている。 ジョナゴールドは全国の約80%を青森県で生産されている。収穫時期は10月~11月頃である。その時収穫したものが春先まで出荷される。 特徴 ジョナゴールドは300gぐらいの大きさで、淡いピンクがかった赤色である。果肉はシャキシャキして硬く、果汁も多く、甘さと酸味のバランスも良い。紅玉によく似た品種なので、煮ても煮崩れしにくいが、紅玉よりも酸味は弱い。 旬の時期より収穫が早いものは酸味が強く、長期貯蔵されているものはスカスカなものも多いため、選ぶときは旬に収穫したものを選ぶようにするといい。 王林 王林は「ゴールデン・デリシャス」と「印度」の交配品種で、青りんごの代表的な品種となっているものの、品種登録はされていない。 王林は比較的有名なりんごで青森県で最も多く生産しており、全国の76%を占める。王林の収穫はりんごの中では遅めで、10月中旬頃から、11月初旬頃に市場に出回る。11月中旬から翌年の2月頃までが旬と言えるが、貯蔵性が優れているため、4月頃まで出荷されている。 特徴 王林の果実は250~300gぐらいで、果皮は黄緑色の青りんごである。果皮には緑色の斑点があり、果汁は豊富で果肉はやや硬めである。酸味が弱く、甘さが強く、独特な香りがあるところが特徴である。 サビが出やすいところがあり、地元では市場に出せないようなB級品が比較的出回っている。
• いちごの品種(国産)
あまおう®(福岡S6号) 「あまおう」の主な産地は福岡県で、2月から5月頃まで市場に出回る。 「あかい・まるい・おおきい・うまい」の頭文字から名付けられている。 「あまおう」はほかのいちごに比べてサイズが大きく丸みのあるフォルムで、大粒で重みのあるところが特徴である。甘味が強く、味が濃いため、人気の高いいちご。 おいしい「あまおう」を見分けるには、紅色の濃いものを選ぶとよい。色が黒っぽい紅色だったり、紅が濃すぎるものは鮮度が落ちているため、色の黒いものは使用を避けるようにする。細いものよりころんとした形の丸いものの方が風味がよい。水分が非常に多いため、一度切ってしまうとかなりしなびやすくなるので注意が必要。 とちおとめ 「とちおとめ」の主な産地は栃木県で、11月頃に出始め、6月頃まで市場に出回る。 「とちおとめ」は東日本のシェア1位を誇る品種で、糖度が高く甘さが強い点が特徴である。比較的大粒のものが多く、果汁が豊富で糖度も高い。 おいしい「とちおとめ」を見分けるには鮮やかな赤色を選ぶようにするとよい。見た目は大粒のほうが良品とされるが、大粒も小粒も味には大きな違いがなく、どちらも甘く果汁が多い。 果肉の色が淡いため、断面がきれいに見えるので、断面を見せる製品に向いている。 紅ほっぺ 「紅ほっぺ」の主な生産地は静岡県で、12月~5月頃まで市場に出回る。 「紅ほっぺ」の特徴は、その名の通り、果皮や果肉が美しい紅色をしているところにある。また、おいしさにほっぺが落ちるということも表している。長い円錐形で、大粒のものが多い。やや強い酸味がある。 おいしい「紅ほっぺ」を見分けるには、香りのいいものを選ぶようにする。長い円錐形が標準的な形である。 色が薄すぎず、濃すぎないものを選ぶとよい。果肉の色が濃いので、ジャムにすると果肉の赤さが映えてきれいな仕上がりとなる。 さちのか 「さちのか」は長崎県や佐賀県、千葉県などが主な生産地で、12月頃から店頭に並びはじめ、2月から3月頃がもっとも出荷が多く、5月頃まで市場に出回る。 「さちのか」は甘味と酸味のバランスの優れたいちごで、広く栽培され、スーパーなどでも販売が行われているため、知名度の高い品種である。サイズは大粒で、円錐形の濃い赤色をしている。光沢があり果肉は固いため比較的傷みにくく、運搬もしやすい。果肉や中心部は淡い赤色をしている。 おいしい「さちのか」の見分けるには、色の濃く・甘い香りのするものを選ぶとよい。鮮度が落ちているものは黒っぽくなっているので使用は避ける。 さがほのか 「さがほのか」の主な生産地は佐賀県で、12月頃から店頭に並び、3月頃もっとも出荷が多くなり、5月下旬頃まで市場に出回る。 「さがほのか」は酸味が控えめで甘味が強く、果汁が多めである。光沢のある紅色の果皮と白い果肉のコントラストが美しいところも特徴である。円錐形で大粒のものが多い。 おいしい「さがほのか」を見分けるには、全体的に鮮やかな紅色のものを選び、つやがないものや色の薄いもの、黒っぽいものは選ばないようにする。鮮度の高いものは香りが立つので、香りのいいものを選ぶとよい。 「さがほのか」は香りが強いいちごなので、いちご風味を強く出したいケーキなどに使うと良い。