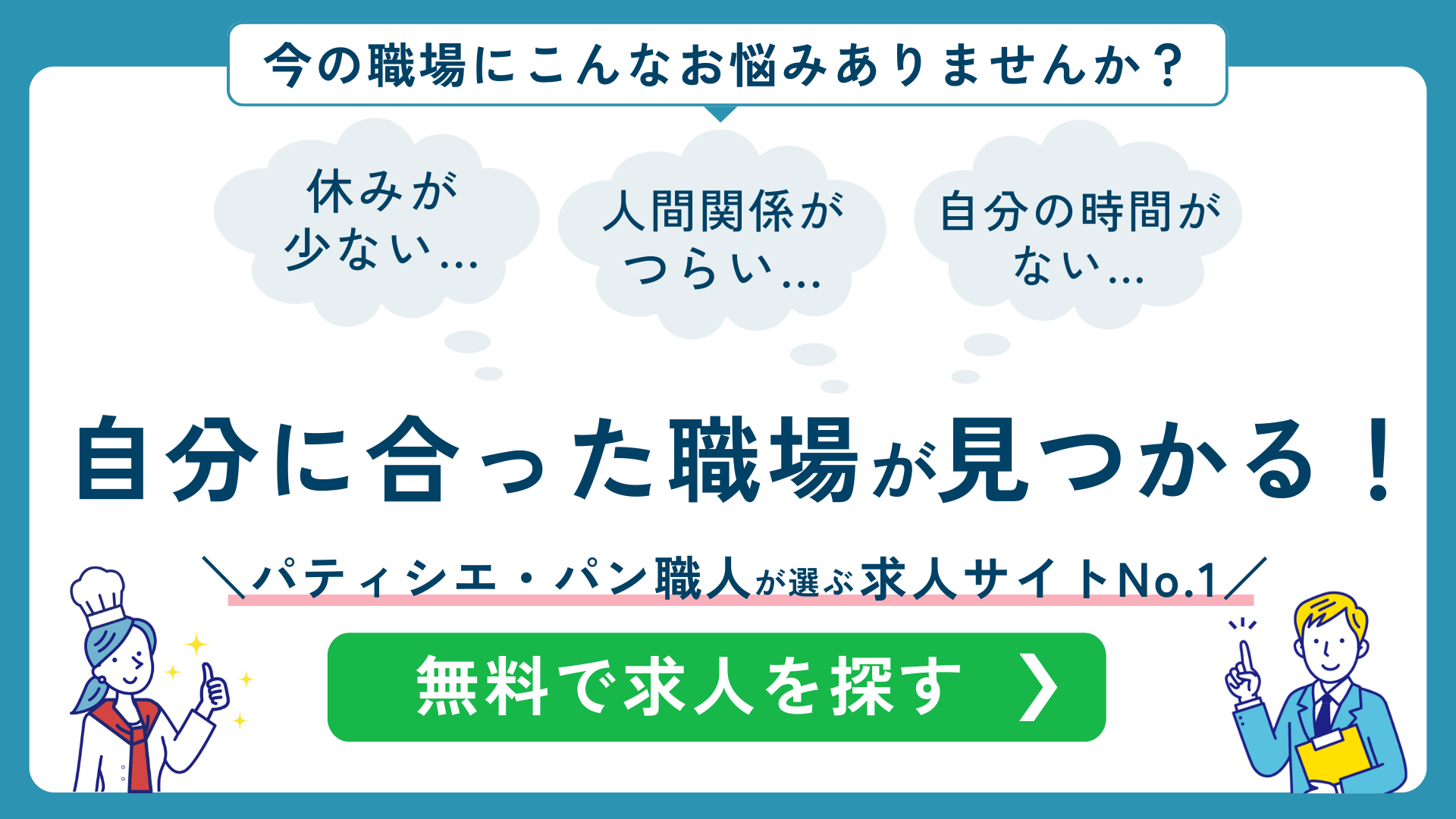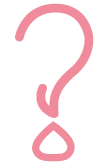
牛乳
カテゴリ:乳製品

120〜150℃で1〜3秒で超高温瞬間殺菌が行われている。
原料に生乳以外の物を一切含まない。
乳脂肪3%以上、無脂乳固形分8%以上で、15℃における比重1.028〜1.034。
牛乳は乳牛の種類や飼育環境により成分がかなり変わってくる。
日本では乳固形分の量はあまり多くないが、泌乳量の多く、食肉用としても転用できるホルスタイン種が主に飼育されている。
生産量は少ないが濃厚で風味が良いとされているジャージー種の牛乳もある。
牛乳を加工して、ヨーグルト、チーズ、生クリーム、バターなどの乳製品が作られる。
卵と相性の良い食材。卵と牛乳を主原料として、カスタード、アングレーズソース、プリンやアイスクリームなとが作られている。
牛乳の種類
低温殺菌牛乳
低温保持殺菌法で殺菌した牛乳。独特の風味がある。→牛乳の殺菌法
ノンホモ牛乳
下記のホモジナイズ(ホモゲナイズともいう)を行わない牛乳。牛乳容器の上の方にクリームの層(クリームライン)ができるので、よく振って使用すること。加工乳
生乳に脱脂乳やクリームなどの乳製品を加えて乳成分を調整した物。乳脂肪に関する規定がない。濃厚牛乳や低脂肪牛乳(ローファットミルク)はこれに分類される。牛乳は季節によって成分が変動するか、加工乳には成分変動がない。
加工乳を使えば一年を通して、安定した製品を作ることができる。
脱脂粉乳(スキムミルク)生乳からほとんどの乳脂肪を除いて、粉末にしたもの。
更新日:2018年12月11日
作成日:2018年09月12日
更新日:2018年12月11日
作成日:2018年09月12日
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの協力のもと制作されています。
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの
協力のもと制作されています。
関係項目
• 牛乳の殺菌法
牛乳は法令に基づき、飲用目的で牛乳を消費する場合には必ず殺菌することが義務付けられている。生乳には病原菌や腐敗菌など多くの菌が存在し、それを殺菌することによって減少させる必要があるためである。 高温短時間殺菌法 高温短時間殺菌法は『High Temperature Short Time』と言われ、その頭文字をとって『HTST』とも言われている。摂氏72度~75度、15秒以上の高温短期間で加熱し殺菌する方法である。もとは欧米諸国で使われていた方法だが、日本にも導入され急速に普及した。加熱と冷却を繰り返し効率よく殺菌させ、大量に殺菌ができるだけでなく牛乳が密閉された中で行われるため、衛生面でも優れている。 高温保持殺菌法 高温保持殺菌法は『High Temperature Long Time』と言われ、その頭文字を取って『HTLT』とも言われている。摂氏75度以上の高温で15分以上の長い時間をかけて殺菌することが条件となっている。高温短時間殺菌法を、より進化させ高温かつ長時間に牛乳の殺菌を行う方法である。 超高温瞬間殺菌法 超高温瞬間殺菌法は『Ultra High temperature Treatment』と言われ、その頭文字を取って『UHT』とも言われている。摂氏100度以上の超高温で、数秒という一瞬のみ牛乳殺菌処理する方法で、現在日本の牛乳殺菌法の主流となっている。日本国内で大量に牛乳を消費するようになったため、この殺菌法が使われるようになった。 超高温処理殺菌法には間接加熱法と直接加熱法の2種類がある。 間接加熱法は牛乳と加熱媒体が壁で仕切られて別に置かれていて、熱交換によって加熱殺菌される方法で、コストが安い点が特徴である。 直接加熱法は牛乳の中に直接加熱蒸気を吹き込む方法で、蒸気でいっぱいになっている容器の中に牛乳を吹き込む。この方法では、牛乳の過熱と冷却が急速に行えるため、加熱部分に牛乳内のたんぱく質の沈着が軽減できる。それによって、長時間機械の運転が可能になるが、ランニングコストが高くなるという特徴がある。 低温保持殺菌法 低温保持殺菌法は『Low Temperature Long Timeと言われ、その頭文字を取って『LTLT』とも言われている。摂氏62度~65度の低温で、30分間以上の長い時間をかけて牛乳殺菌する方法である。基本的な牛乳殺菌法ともいえるが、作業効率が悪いため、今では全体の2%ぐらいしかこの方法は使われていない。低温でじっくりと殺菌する点で、高温殺菌の他の方法よりも牛乳の風味が損なわれないというところが特徴である。
• 生クリーム
牛乳のみを主原料とし、乳脂肪18%以上、無添加で衛生基準を満たしたものを「クリーム」という。 「クリーム」は生クリームの法規上の正式な名称。牛乳の中にある乳脂肪は脂肪球という粒の形をしており、それを遠心分離により濃縮した物。 用途に合わせて色々な種類のものが開発されている。業務用は牛乳と同じ1リットル入りの紙パックの物が多い。 やや黄色みを帯びた白色で、風味、口溶けに優れている。乳脂肪が多いクリームほど黄色っぽい。この色みは乳牛の食べる牧草由来のカロテノイド色素によるものである。 「クリーム」に乳化剤と安定剤を入れた物も生クリームと呼ばれることもある。 乳脂肪と安定剤は味に影響しない。生乳のみを原料としているものより賞味期限が長く、分離しにくくて保形性も高いので扱いやすい。 乳脂肪量 乳脂肪分20〜30%の物はコーヒーに加えるために作られたもの。 コーヒーの苦味を抑えてマイルドな味わいにする。 コーヒー本来の風味や旨みを邪魔しない、低脂肪のクリームが好まれる。 35%の乳脂肪分がなければ、泡立てることができない。 一般的に35〜38%の低脂肪の物と、40〜45%の高脂肪の物とを製品に合わせて使い分けたり、混ぜて使ったりすることが多い。 →乳脂肪と植物性脂肪 製菓においての生クリームの重要性 生クリームが使われるケーキと言えば代表的なのは苺のショートケーキ。 老若男女から根強い人気があり、今でも多くの店で売れ筋のケーキになっている。 このケーキに大量に使われる生クリームが店のイメージを決めると言っても過言ではない。 生クリームの味はメーカーや種類によってかなり違いがあり、生クリームの選び方がお店の味の個性になるともいえる。