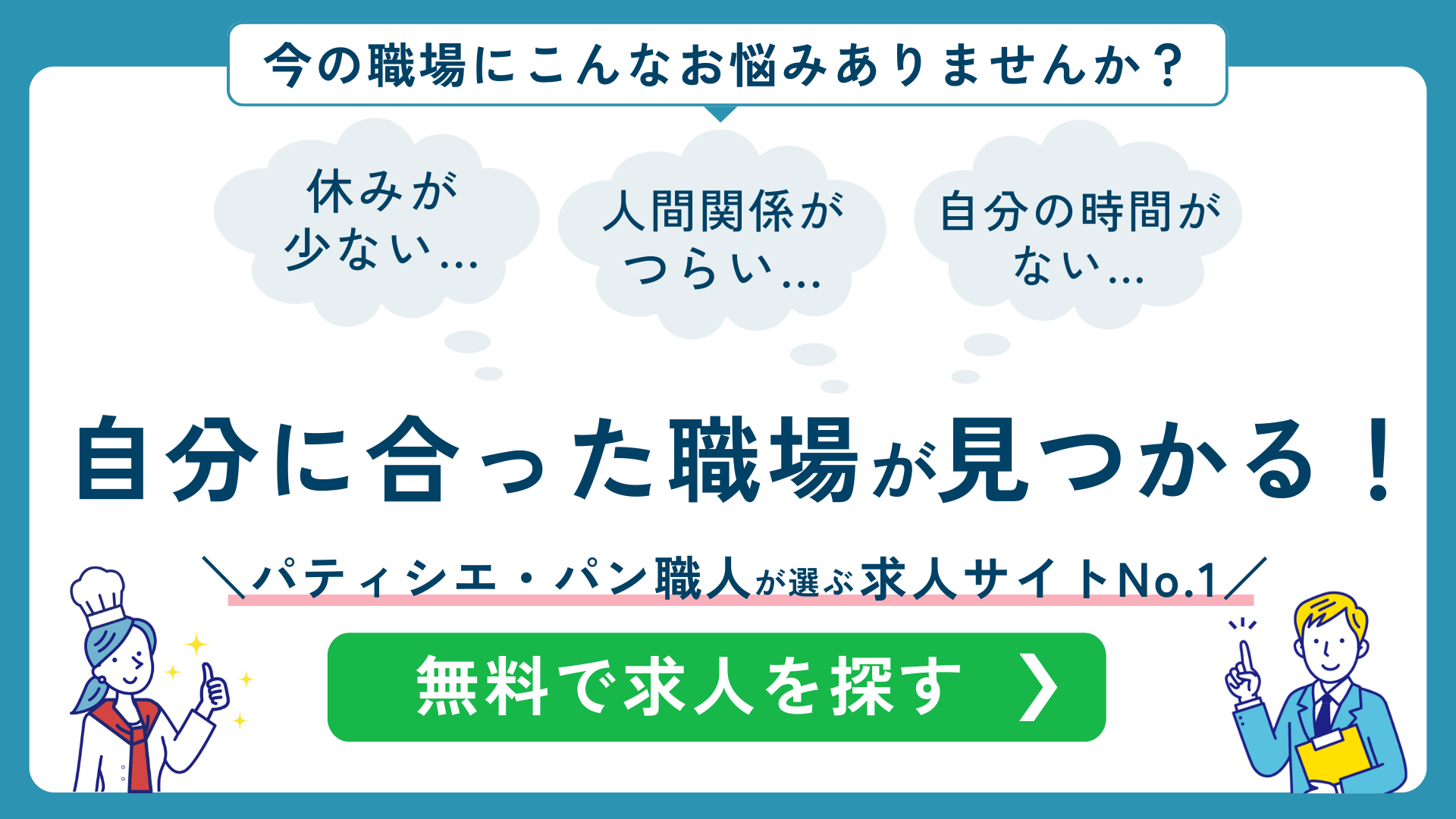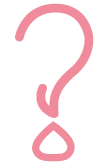
化学物質による食中毒
カテゴリ:食中毒
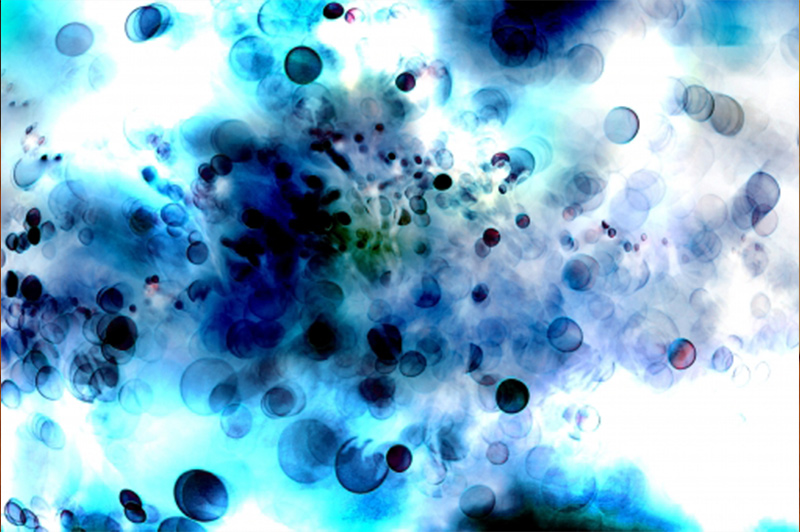
季節によって左右される事はない。添加物は食品衛生法により取り締まっているが、不良業者が有害品を使用する事がこれまでにあった。
原因
有害食品添加物が主な原因。特に多いものは、農薬や有機水銀。添加には規制があるが過剰摂取したときに食中毒が起こる。有害保存料、有害着色料、有害甘味料、有害殺菌料、有害漂白量、有害調味料がある。
残留農薬や、有害金属。(漂白剤兼防腐剤、ヒ素、銅、鉛、亜鉛、カドニウムなど、規格外の使用で食中毒が起こったこともある。中には、発がん物質のものもある。
症状
原因によってさまざま。のどの痛みや吐き気、胃腸、腎臓、神経、肝臓に障害が起こる事があり、量によっては生命にかかわる。
更新日:2019年07月30日
作成日:2018年09月13日
更新日:2019年07月30日
作成日:2018年09月13日
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの協力のもと制作されています。
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの
協力のもと制作されています。
関係項目
• ノロウイルス
ノロウイルス【英:Norovirus】 直径30nm前後で小型球形の構造を持つ。細菌よりも小さく、電子顕微鏡でなければ見ることができない。 細菌のように食品中で増えることはなく、ウイルス粒子だけでは増えることができないため、人以外には感染せず、人間の体内(小腸粘膜)でしか増殖することができない。pH2~3程度の酸にも強いため胃酸にも影響されず、胃を通過して腸管に感染する。このウイルスは感染力が強いため、10~100個の少量のウイルスで感染が起こるとされる。 また、熱耐性も強いため、60℃30分の加熱処理では病原性を失なわず、殺菌剤(4~6ppm)や消毒用アルコールに対しても抵抗性がある。 原因 食品からの介入 1.ウイルスを含む食材(カキなどの二枚貝が中心)や飲料水を生のまま、加熱不十分で摂取した場合 2.ウイルスに汚染された調理台・調理器具を使ったり、感染者が十分に手を洗わずに調理することにより二次的に汚染された食品を食べた場合 人から人への二次感染 1.感染者の便や嘔吐物、それらに汚染された器物や衣類に触れた手指を介して他者に伝播し、経口感染(接触感染) 2.感染者の便や嘔吐物が周囲に飛散し、経口感染(飛沫感染) 3.感染者の便や嘔吐物が乾燥し、ウイルスが空気中に舞い上がって漂い、経口感染(空気感染) 症状 主な症状は、風邪に似た症状、腹痛、吐き気、下痢、嘔吐、発熱(38℃以下)、頭痛などである。一般に症状は軽く、感染しても風邪のような症状で済む人もいるが、乳幼児や高齢者では重症化することがある。症状が改善した後も、少なくとも1週間はノロウイルスの排出が続き、ウイルスは人体外環境で長く生存する。 予防 ノロウイルスは、85℃以上で1分以上の十分な加熱が有効である。 調理器具等は、洗剤等で十分洗浄した後、熱湯消毒か、塩素系消毒剤で消毒を行う。 調理前・食事前・用便後は、流水・石けんで手洗いをしっかり行う。消毒用アルコール製剤の使用も有効である。
• セレウス菌
セレウス菌とは土壌細菌の一種。食中毒を引き起こす菌である。 原因 菌は自然界(土壌、河川)に広く生息している。熱に強い細菌であり、100℃30分の加熱にも耐える。大きく「嘔吐型」と「下痢型」に分類される。日本での発症は「嘔吐型」が多く報告されている。下痢型は摂取した後、小腸で毒素を作り食中毒を発症させ、欧米での発症が多い。 (嘔吐型の原因食品) チャーハン、ピラフなどの焼き飯類 焼きそばやスパゲッティーなどの麺類(麦が原料) (下痢型の原因食品) ソーセージなど加工肉類 野菜類、またそれらを使用したスープなど 症状 嘔吐型 吐き気や嘔吐(潜伏期間1~5時間で発症) 下痢型 腹痛や下痢(潜伏期間8~16時間で発症) 予防方法 調理する際は十分に加熱、また調理後に室温に放置しない。