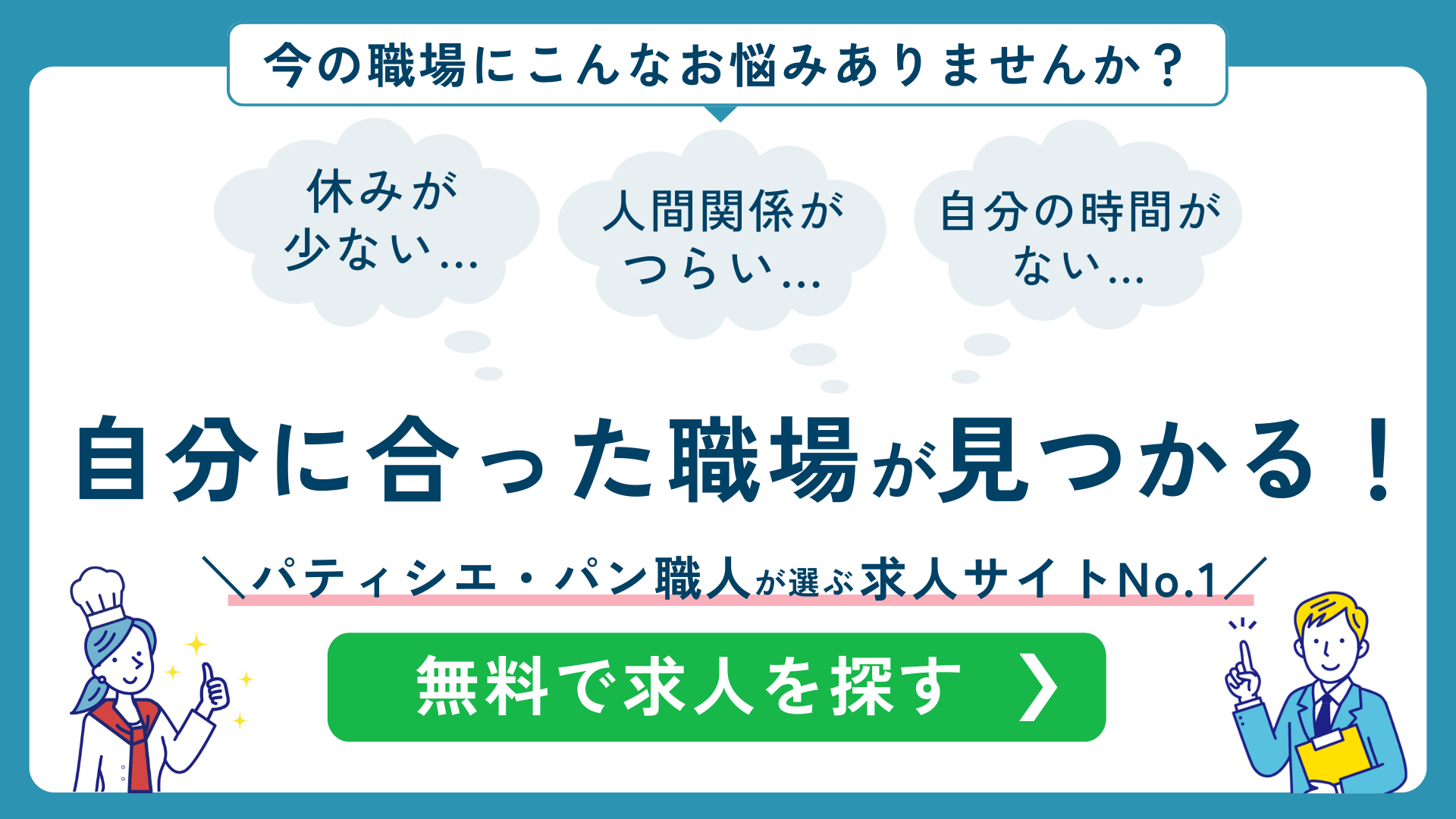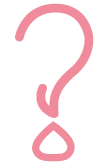
タミゼ
カテゴリ:仕込む

薄力粉などの粉類を『ふるう』こと。
生地などを仕込む際に粉類をふるうのは、混ぜる工程で粉のダマができるのを防ぐため。ダマができたまま生地を仕込むと材料が均一に混ざらず、粉のかたまりができたまま焼きあがってしまったり、焼き上がりにムラがでたりすることがある。
ふるうことで大きなかたまりやゴミなどを取り除くことができるため、粉類の計量はふるいにかけてから行うのがよい。
ふるった粉をボウル等に入れておくと、ふるって細かくなった粒子が底にたまって再び固まり、あわせる材料の中で分散にしくくなってしまう。
粉はできるだけ生地にあわせる直前に紙の上でふるい、そのままおいておくとよい。ふるうことで粉の粒がほぐれ、空気が入ってふんわりとするため、生地に混ざりやすくなる。
ケーキの仕上げの際に粉砂糖やココアパウダーをふるうときは、茶こしを使用するとムラができない。
更新日:2018年12月11日
作成日:2018年10月16日
更新日:2018年12月11日
作成日:2018年10月16日
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの協力のもと制作されています。
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの
協力のもと制作されています。
関係項目
• 小麦粉
世界で栽培される小麦は、栽培の季節によって春小麦と冬小麦にわかれる。 小麦は粒の色の違いで赤小麦と白小麦に分けられ、さらに粒の硬さによって硬質小麦、中間質小麦、軟質小麦に分けらる。 分けられた小麦をいろいろと組み合わせ、小麦を挽き、胚乳の部分を粉にしたものが小麦粉である。 全粒から果皮や胚芽の部分はふすま(皮くず)として除去し、胚乳の部分のみを挽いたもの。全粒100kgから、おおよそ75kgの小麦粉が得られる。 同じ小麦の胚乳部分でも、中心部は灰分が少なくなっている。中心部分の方が白く、たんぱく質の量も少なくなる。 主にこの中心部分からとれるものは上級粉といわれ、灰分が低く、乳白色または淡黄色の冴えた色をしている。表皮近くからとれる下級粉は、たんぱく質が多くなって、色がくすみ茶褐色を帯びてくる。 →灰分と小麦粉の等級 →小麦粉の種類 小麦粉の性質 小麦粉は水を加えて練り合わせると「グルテン」というタンパク質が網目状に変質して、つきたてのモチのような「粘弾性」をもつ物質に変わる。 このグルテンはお菓子作りでは欠かせないもので、生地の骨格を形成する非常に重要な役割をもっている。 でんぷんに熱を加えるとのり状になり、その状態を糊化(α化ともいう) 米に水を加え、加熱して炊飯すると粘りが出るのと同じ現象である。 糊化した物が乾燥したものを老化という。老化した状態はもとには戻らない。 炊きあがった米を出しっぱなしにして固くなったものは水を加えてもとに戻らないのと同じであり、老化した小麦粉の状態が元に戻ることはない。 ケーキ作りにおいて、スポンジ生地などのパサつきの原因になったり、しっとりしたりする原因にはこの糊化、老化の作用も大きく関係している。
• タミ
タミ【仏:Tamis】 粉などを振るいにかけるための器具。振るい器。 両サイドに手を添えて横に大きく動かすことで、あちこちに飛び散ることなく速く振るうことができる。 ペーストなどの裏ごしに使われることもあるが、網が強くないものが多いので、硬いものの裏ごしには向かない。強い力を加えると簡単に壊れてしまう。 また、水を吸った粉の塊や繊維が網目に残りやすいため、丁寧に洗う必要がある。