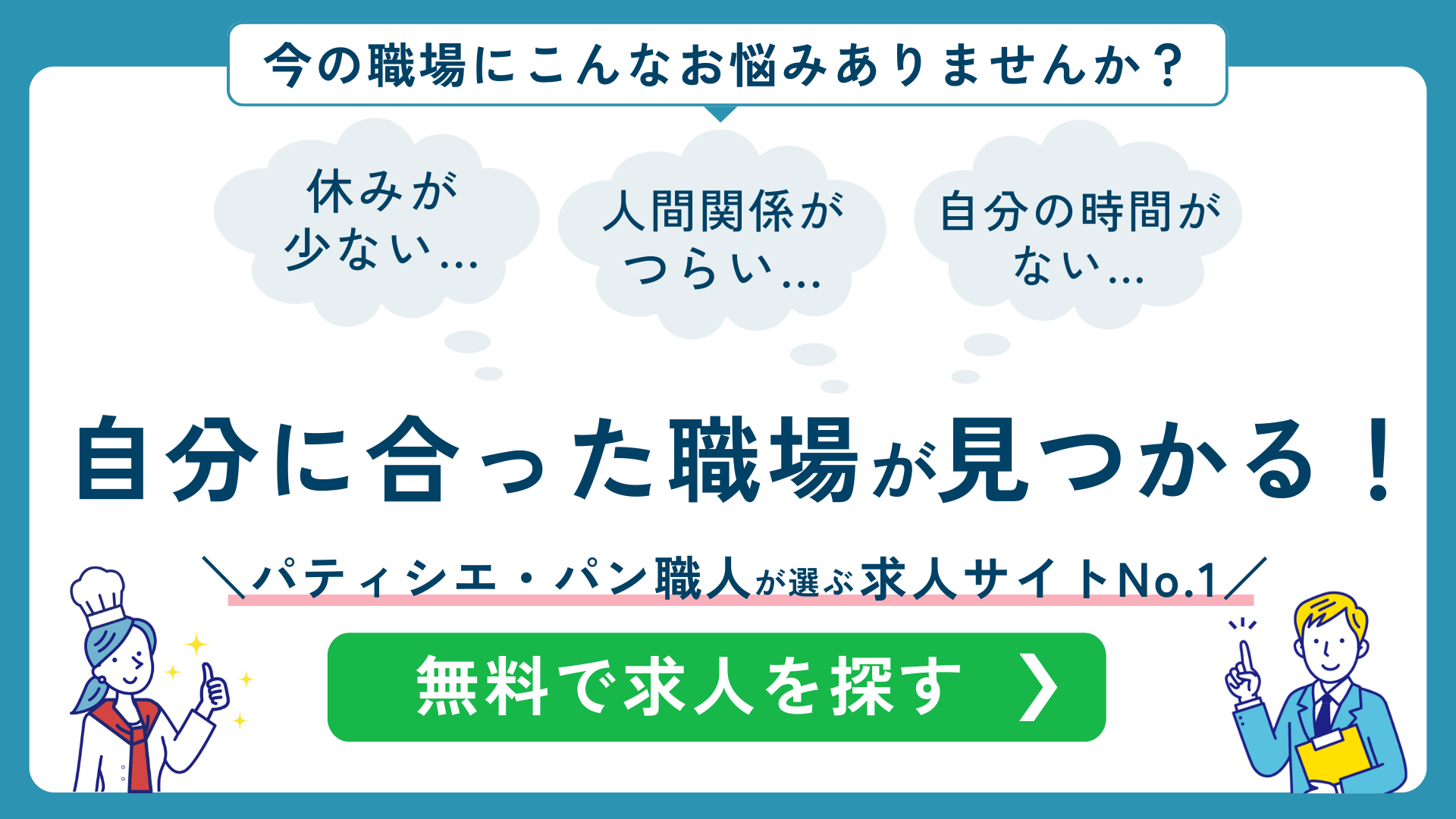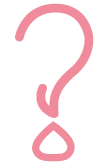
グレープフルーツ
カテゴリ:果物類

柑橘類の一種でミカン科ミカン属グレープフルーツ種に属し、亜熱帯を原産とする。ブドウのようにたわわに実るところからグレープフルーツと呼ばれるようになった。グレープフルーツは品種も多く、果肉の色で分類されている。
日本の市場に出回っているグレープフルーツのほとんどは輸入品であり、アメリカ産が7割。アメリカ産グレープフルーツの旬は11月~6月である。6月~11月は南アフリカ産のグレープフルーツが入ってくるため、日本では1年を通じて市場に出回っている。
グレープフルーツは木に成り、果実は10〜15cmほどのソフトボールのような球状で、黄色い色をしている。表面はでこぼこしていて、白やピンクの果実が房に分かれている。
果汁が豊富で、甘味が淡くて酸味が強い。ほろ苦さがあるさっぱりとした味わいが特徴である。
グレープフルーツは、形が丸く整っていて、ハリとつやがあるずっしりと重たいものを選ぶとよい。
果皮がごわついているものは、果実がスカスカになっているものもあるので選ばないようにする。果皮にシミのついたものもあるが、味には影響していない。
ぶどうのようにほかの実と重なって実るため、形がいびつなものはそれだけほかの果実が近くにたくさんあったことを表その分栄養素が十分行き届いていないことがある。
果皮には農薬がついているのでよく洗う必要がある。
グレープフルーツの種類
ホワイトマーシュ
ホワイト系の方が酸味が強い。日本でよく見る一般的なグレープフルーツで、果皮は黄色、果肉は白黄色。果汁が多く苦みもあるが、さわやかな味をしている。
ピンクマーシュ
いわゆるピンクグレープフルーツ。果皮はホワイト・マーシュと変わらぬ黄色だが、果肉は薄いピンク色をしている。
生産数が少なく、あまり流通していない。
ルビー、スタールビー
果皮は黄色〜オレンジやピンクのものもあり、果肉は赤みがかった色をしている。
ホワイト種に比べて苦味が少なく、甘みが強く感じられる。
保存方法
風通しの良い冷暗所か冷蔵庫の野菜室に入れておくと1~2週間ぐらいもつ。切ったものはラップで乾燥しないようにして早めに使い切るようにする。注意点
ゼリーを作る際などにゼラチンを使うと、グレープフルーツの酸が反応しうまくかたまりにくい。ゼリーを作る際にゼラチンを使う場合は果汁の量を減らす、もしくは、ゼラチン以外の凝固剤を使う必要がある。また、グレープフルーツの果肉に含まれる成分は高血圧治療薬などの特定の医薬品と相互作用し、これらを服用している人には摂取が制限されているので、食用には注意する必要がある。また、風邪薬などにも作用し、効き目が強くなるということがある。
更新日:2018年12月11日
作成日:2018年09月07日
更新日:2018年12月11日
作成日:2018年09月07日
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの協力のもと制作されています。
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの
協力のもと制作されています。
関係項目
• オレンジ類
オレンジ【和:アマダイダイ、英:orange(オレンジ)、仏:orange(オラーンジュ)】 オレンジはミカン科ミカン属の常緑小高木、またはその果実を指し、柑橘類に属する。インドのアッサム地方が原産とされており、国内に輸入されるオレンジのほとんどはアメリカ産である。 日本にあるオレンジは バレンシアオレンジ 、 ネーブルオレンジ 、 ブラッドオレンジ に大別される。 オレンジは果皮、果肉共にオレンジ色で果汁が豊富である。香りが高く甘味と酸味を合わせもつ。ジュースの原料としてよく利用される。また肉の料理のソースとしてもよく用いられる。 果皮は砂糖漬けにしてオレンジピールに使われたり、キュラソーの原料としても使われる。果皮と果実の入っている袋の部分がくっついていて離れにくいため、皮を向かずに輪切りやくし切りにしたり、スプーンでくり抜いたりして食べることも多い。 オレンジの種類 バレンシアオレンジ【英:Valencia orange】 最もオーソドックスなオレンジ。「バレンシア」という地名はスペインだが、「バレンシアオレンジ」はアメリカの品種で、日本にもアメリカのカルフォルニア産のものが多く輸入されている。 バレンシアオレンジの旬は夏で、カリフォルニアでは6月から11月にかけて収穫される。 バレンシアオレンジは皮が硬く、ナイフなどで剝かなければ剥けない。全体的に味のバランスがよく、オレンジの中では酸味も多い。果肉もしっかりと締まっていて弾力があり、房取りもしやすい。他のオレンジとの見分け方としては、果頂部に茶色い点があるところが特徴である。 ジュースにしても絞った果汁が劣化しにくく、加熱しても味が安定しているため使いやすい一面もあるが、種が多いものもある。 ネーブルオレンジ【英:Navel-orange】 主にアメリカのカルフォルニアから輸入されていて、12月頃から3月頃までが旬となっている。国内でも和歌山県を中心に大三島ネーブル、白柳ネーブル、吉田ネーブルなどの品種が2月~3月頃出荷されている。 ネーブルオレンジの果実はやや縦長の楕円形をしている。果頂部にへそ状の窪みがあり、これが名前の由来となっている。ネーブルオレンジの果皮は薄くて手で剥くのは難しいため、通常はナイフで皮を剥く。味が濃く、甘みも酸味もとに強く香りもよい。また、バレンシアオレンジとは違い、種もほとんど無い。果肉が底の部分で分化しているため、小さな房になっていて、房取りがしにくくなっている。 果汁が劣化しやすく日持ちしないため扱いにくいのが難点。 ブラッドオレンジ【英:blood orange】 果肉が紅いオレンジの総称を言い、血のように赤いところからこの名がついたと言われている。ブラッドオレンジにはタロッコ種、モロ種、モロ種によく似たサングイネッロ種がある。 アメリカ産モロ種のブラッドオレンジは1月中旬からから5月頃までが旬で、国産のモロ種は4月中旬から6月にかけてが旬である。イタリア産タロッコ種は4月中旬から5月まで、国産タロッコ種は4月中旬から6月下旬までが旬である。国内では愛媛県で多く作られている。 他のオレンジと比べると果実がやや小ぶりで、他のオレンジと同じように果皮にの表面に小さなくぼみが見られる。果肉は、ブラッドオレンジという名の通り、血のような濃赤色をしている。これはアントシアニンの色素によるものだが、柑橘系の中では珍しい。甘味の強いオレンジであるが、オレンジの突然変異種とも考えられている。
• レモン
レモン【和:檸檬(れもん)、英:Lemon(レモン)、仏:Citron(シトロン)】 レモン(学名: Citrus limon)は、ミカン科ミカン属の常緑低木で果実は柑橘類である。 レモンの出回る時期は秋冬で10月~3月頃だが、輸入のものも多く1年を通じていつでも手に入る。国内での主な産地は広島で、広島だけで国内のレモン生産の半分以上を占める。 楕円形に形が整っていて果皮にハリとツヤ、弾力があるものが良品とされている。その中でも軸の部分が緑色で香りがよく色鮮やかなものがよい。重みがあるもののほうが軽いものより水分がありおいしい。古くなると皮にシワが入ったり、変色したりする。 ビタミンCが多く含まれていて、風邪予防、美容などに効果を発揮する。また、クエン酸も豊富に含まれているため、疲労回復にも役立つ。 保存方法は、常温の場合冷暗所で保存。この場合数日で使い切る必要がある。 さらに長持ちさせたい場合は乾燥を防ぐためポリ袋に入れて冷蔵庫で保存する。5~6℃くらいの環境で約1ヶ月ほど保つ。カットしたレモンは早めに使い切るようにした方がいいが、保存するときは切り口をラップで包んで冷蔵庫へ入れて保存する。 レモンピール(加工品) 製菓でよく使われるレモンの使用法として、レモンの皮を砂糖で煮つけて、上からグラニュー糖をまぶしたレモンピールがある。生ケーキなどの洋菓子にも使用されることが多い。