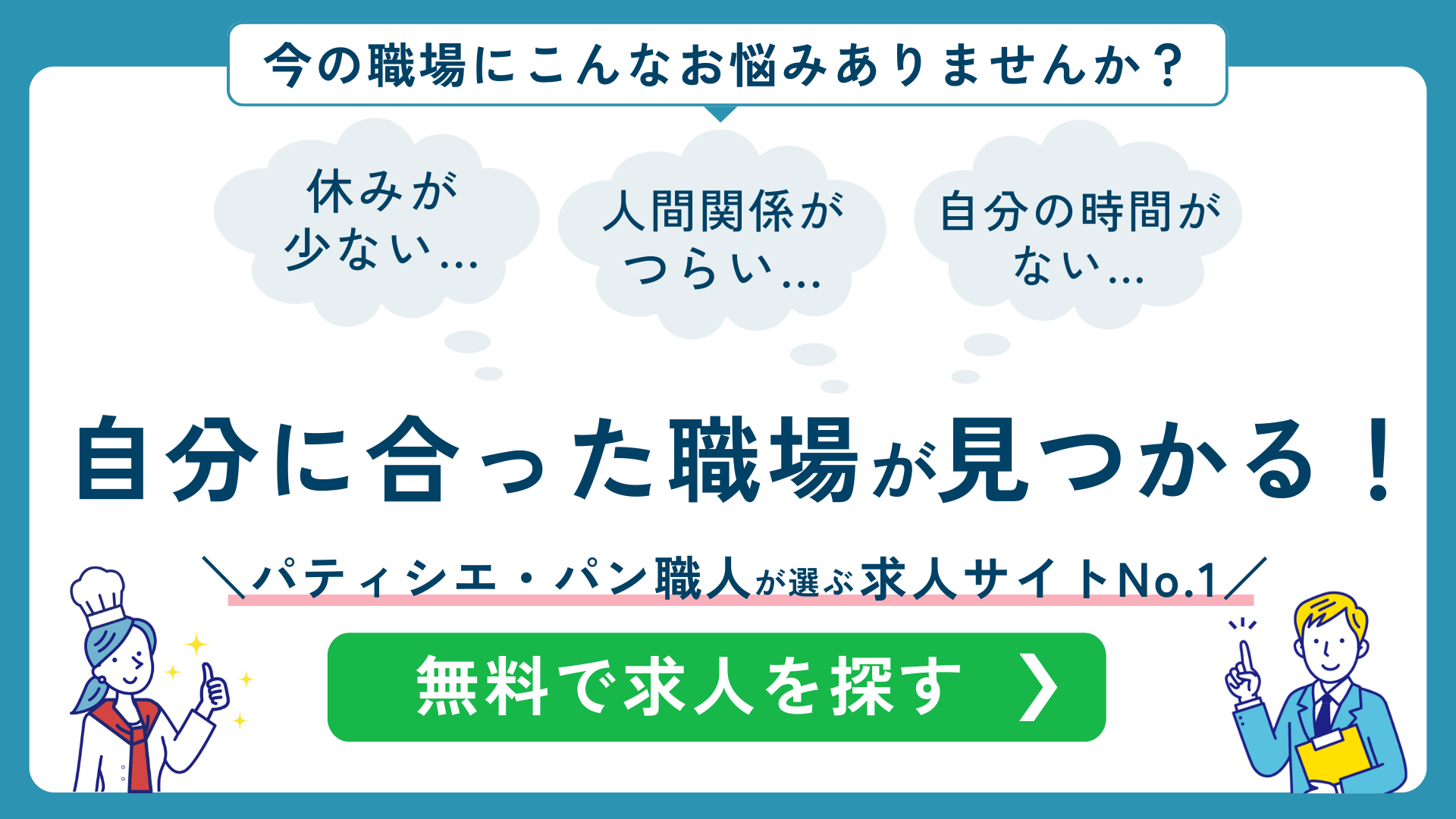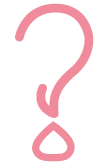
ボンボン・ア・ラ・リキュール
カテゴリ:糖菓

日本でいうボンボン菓子のことで、お酒を閉じ込めた菓子のことをいう。
一般には砂糖でできた殻でお酒を閉じ込めるが、日本ではチョコレートの殻で閉じ込めたショコラ・ボンボンが有名である。中でもウイスキーが使われたものは、ウイスキーボンボンと呼ばれる。チョコレートの甘さとお酒のほろ苦さが同時に楽しめる点が魅力的。
ボンボン・ア・ラ・リキュールの中に入っているお酒はアルコール度数がおおよそ2%~3%のものが多い。
歴史
ボンボン・ア・ラ・リキュールという名前は、フランス語で良いという意味の『ボン(Bon)』を二回重ね、酒入りという意味のア・ラ・リキュールと合わせられたもので、良いお酒入りのものという意味になる。もともと中世のフランス宮廷で権力者の好物として広まり、日本でも舶来の高級品とし、て富裕層を中心に食べられていた高級菓子である。
中世のフランスでは、ボンボンのための専用の容器として「ボンボニェール」というものが作られたほど、宮廷の貴族や貴婦人の間で流行した。
更新日:2018年12月11日
作成日:2018年09月12日
更新日:2018年12月11日
作成日:2018年09月12日
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの協力のもと制作されています。
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの
協力のもと制作されています。
関係項目
• さくらんぼ
さくらんぼ【和:桜桃(おうとう)、英:cherry(チェリー)、仏:ceries(スリーズ)、独:kirsche(キルシュ)、伊:ciliegie(チリエジャ)】 バラ科サクラ属の、桜の木で栽培される果実。桜に実をつける「桜ん坊」に由来して、さくらんぼという名で知られている。 観賞用として知られるソメイヨシノは品種改良された桜なので、自家受粉ができず実はつかない。生食用として流通しているさくらんぼのほとんどはセイヨウミザクラ(西洋実桜)である。 品種にもよるが、4月頃に白い花を咲かせ、5月下旬に黄赤色や濃赤色の実をつけ、6月〜7月下旬に熟す。年間の出荷量が増えるのも、同時期となる。 追熟しない果実のため、収穫時が最も美味しいと言われている。 果形は丸みを帯びたハート形、2〜3cmほどの大きさが一般的。薄く艶のある皮に覆われており、実の中心に種を含む。甘味と酸味のある果実で、アメリカ産は甘味が強く、国産は爽やかな甘酸っぱさをもつ。新鮮すぎると苦味を感じることもある。 さくらんぼは追熟しない果実であり、また温度変化に弱く長時間冷蔵すると水分が蒸発し、実が締まって甘味がなくなってしまう。収穫から時間が経てば経つほど本来の味を損なうため、1〜2日の間に生食用として出せない場合、コンポートやジャムといった加工品にするのが望ましい。 サワーチェリー さくらんぼの品種の中でも特に酸味の強いもの。日本では「スミミザクラ(酸実実桜)」と呼ばれている。酸味が強いため生食には不向きで、砂糖漬けにしたりリキュールや蒸留酒の原料などの加工品、料理に用いられることが多い。 グリオット(griotte)、アマレル(amarelle) などの種類がある。 スイートチェリー さくらんぼの中でも甘味があり、主に生食用として流通している品種の総称。 ギーニュ(guigne)、ビガロー(bigarreaux) などの種類がある。 さくらんぼの加工品 ドレンチェリー さくらんぼの種を取り除き、砂糖で煮詰めて水分を飛ばし、着色したもの。主に焼き菓子に混ぜたりトッピングとして使われる。
• 醸造酒
醸造(じょうぞう)酒は、酵母により原料をアルコール発酵させて作られた酒を指す。アルコール発酵させたまま蒸させないため、アルコール度数は低い酒になる。 最も代表的な醸造酒は、ワイン、ビール、日本酒で、西欧諸国は果実を発酵させて造る酒が、欧州から中東、アフリカ大陸にかけては穀物の種子を発芽させた酒が、日本を含む東アジア一帯は麹を使った酒が伝統的に作られていた。 醸造酒の種類と製造方法 醸造酒は大きく分けて、「単発酵酒」と「複発酵酒」に分けることができる。 単発酵酒 酵母を加えてアルコール発酵させる酒で、酵母の栄養となる糖分が原料に含まれているものが該当する。例えばワイン(ブドウ酒)、シードル(リンゴ酒)、馬乳酒などである。 複発酵酒 デンプン質を最初に糖に変えたあと、アルコール発酵させるお酒で、原料が米や麦などの穀類の場合などに該当する。 方法は「単行複発酵酒」と「並行複発酵酒」の2種類に分けられる。単行複発酵酒はビールのように穀物を麦芽に変えてデンプンを糖化した後に発酵させる方法を言う。並行複発酵酒は日本酒のようにデンプンを糊化してコウジカビなどで糖化する時に同時にアルコール発酵をさせる方法をいう。