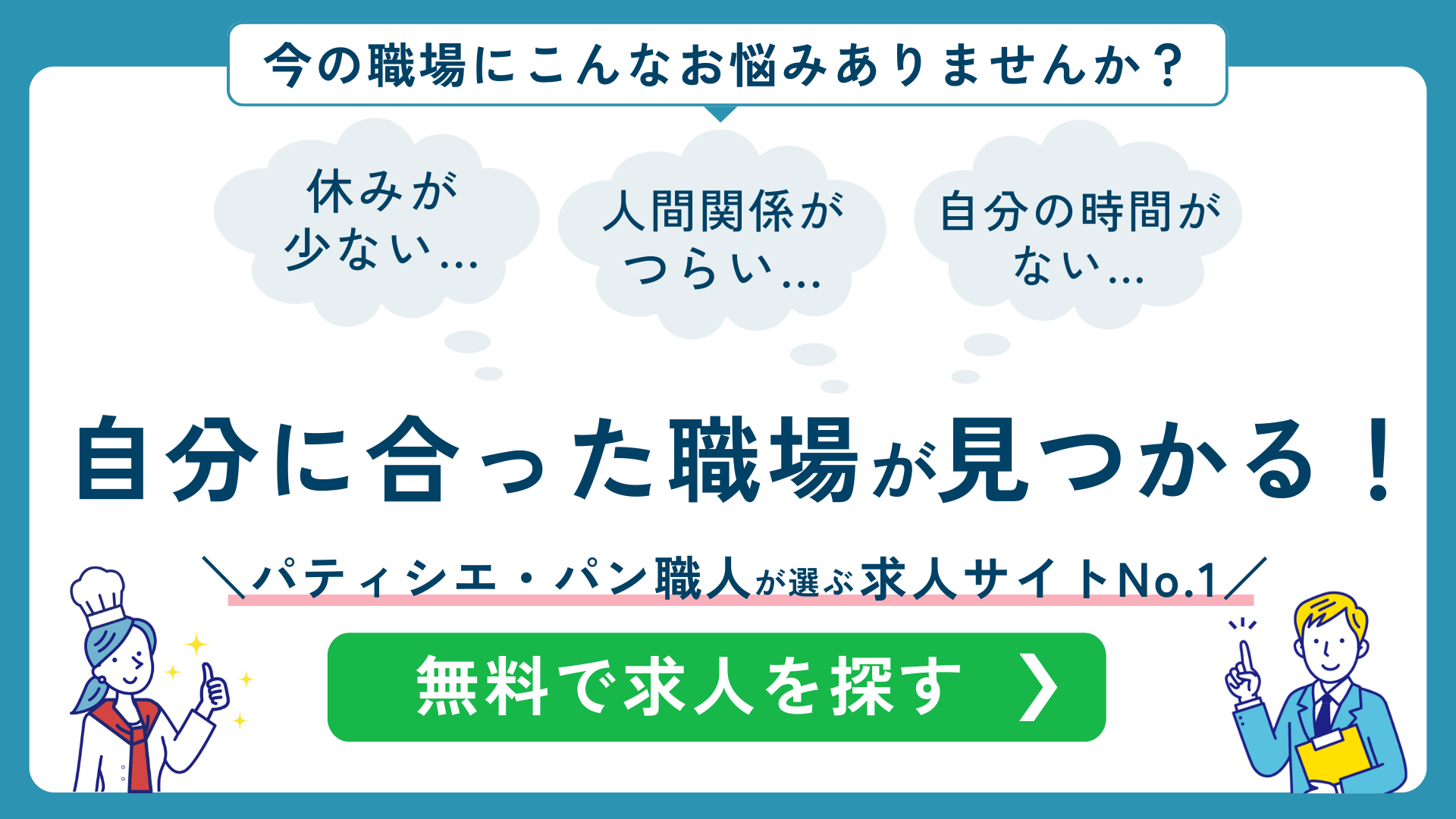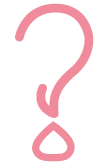
シュー・ア・ラ・クレーム
カテゴリ:シュー生地の菓子

パータ・シューの生地にクリームを詰めたお菓子。
フランス語であるシュー・ア・ラ・クレームはクリーム入りのキャベツ(chou/シュー)という意味合いで、英語ではクリーム・パフ(cream puff)という。
日本でいうシュークリームはフランス語であるシューと英語であるクリームを合わせた和製語。
中に詰められるのは主にクレム・パティシエールやクレム・ディプロマット、クレム・シャンティイなどが主流。
歴史
シュー生地の原型は小麦粉をバターで炒めたルー・ブランから始まったのではないかと考えられているが、他にも「じゃがいもを潰して卵も混ぜたもの」や、「クレム・パティシエール」が始まりではないか、という諸説が存在する。また、他に現代でシュー生地を揚げて作られるべニエ・スフレ(beignet souffiè)に近しいものが、シューの先祖ではないかと言われている。現代で流通しているシューの製法は、1533年にイタリアのメディチ家・カトリーヌ姫がフランスに嫁いだ際に従事していた料理人によってフランスに伝えられ、改良を重ね1760年にジャン・アヴィスが完成させた、いうのが一般論。
日本にシュークリームを伝えたのは、幕末に来日して横浜で西洋菓子店を営んでいたサミュエル・ピエールというフランス人。冷蔵設備が普及した昭和30年代以降には一般庶民にも広まり、シュークリームと合わせてエクレアも親しまれるようになっていった。
更新日:2019年07月09日
作成日:2018年09月12日
更新日:2019年07月09日
作成日:2018年09月12日
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの協力のもと制作されています。
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの
協力のもと制作されています。
関係項目
• パータ・シュー
パータ・シュー【仏:pâté à choux】 シュー生地のこと。 見た目がキャベツに似ていることからフランス語でのキャベツの意味の「シュー」と名前がついた。 パータ・シューを使ったお菓子の中に、シュー・ア・ラ・クレームやパリ・ブレスト、エクレア、サントノーレなどがある。 手順 1.バター、水(牛乳などの水分)、砂糖、塩を鍋にいれ沸騰させる 2.小麦粉を加え加熱しながらしっかりと混ぜ、しっかりと糊化させる 3.ボウルに移し溶きほぐした卵を少しずつ加えていく 4.絞り袋で天板に絞りドリュールを塗り霧吹きで水を吹きかけ窯に入れ焼く ポイント バターは常温に出しておく。冷たい状態だと加熱した時バターが溶けず、水分だけが飛んでしまう。 糊化させる時は鍋肌に生地がくっついてくるくらいまでが目安。 出来上がった生地は上から落としてみてスゥーっと2、3回落ちるくらいの固さがよい。 また、作る物によって炊き上げる生地の固さは変える。 窯は途中で開けると生地がしぼんでしまうので開けないようにする。 最初は下火を強くし、膨らませてから上火をあげて焼成すると色がつく。
• クレーム・パティシエール
クレーム・パティシエール【仏:crème pâtissière】 カスタードクリーム【英:custard cream】 お菓子屋のクリームと言われ、多くのお菓子作りのベースとなるクリームである。 銅鍋を使うことで熱が早く均一に通りやすくなる。 手順 1.牛乳、バニラ、バター、砂糖の一部を入れ沸かす 牛乳はしっかり沸かすこと。バニラは種をとったサヤも入れて良い。 砂糖を少し入れることで、牛乳の膜ができることを防げる。 2.卵黄と砂糖を白っぽくなるまであわせ粉とあわせる 卵黄を砂糖を白っぽくなるまであわせる理由としては、空気をふくませることで火のあたりを柔らかくし、卵黄を煮えにくくするため。 3.沸いた牛乳の一部を卵黄の方に入れ、鍋に戻して炊く 火をかけている際は、ふちの部分についたカスタードをとりながら炊き、均一に熱を通すようにする。 銅鍋の位置をこまめにかえると焦げにくくなる。 ステンレス鍋を使う場合は角が焦げ付かないように意識してホイッパーを動かすこと。 火は強火で、店によっては温度計で温度を確認しながら炊くところもある。 4.バットなどに平たく流し、密着ラップをして素早く冷やす 氷を当てて粗熱をとり、冷蔵庫で保管する。 裏ごしするタイミングは、少量の場合は(3)の時点でアパレイユをボールにすべて移して混ぜた後鍋に戻すとき、量が多い場合はバットに流し込む際に行う。 使用方法 冷やした後、なめらかになるようにゴムベラでまぜ、もどしてから使用する。 この際に裏ごしすると、よりなめらかな仕上がりになる。 生クリームと合わせてディプロマットクリーム、バタークリームと合わせるとムースリーヌになる。 アーモンドクリームと合わせてフランジパーヌとしても使用できる。 シュークリームやフレジエ、ガトーバスク、ポンヌフなどに使われる。