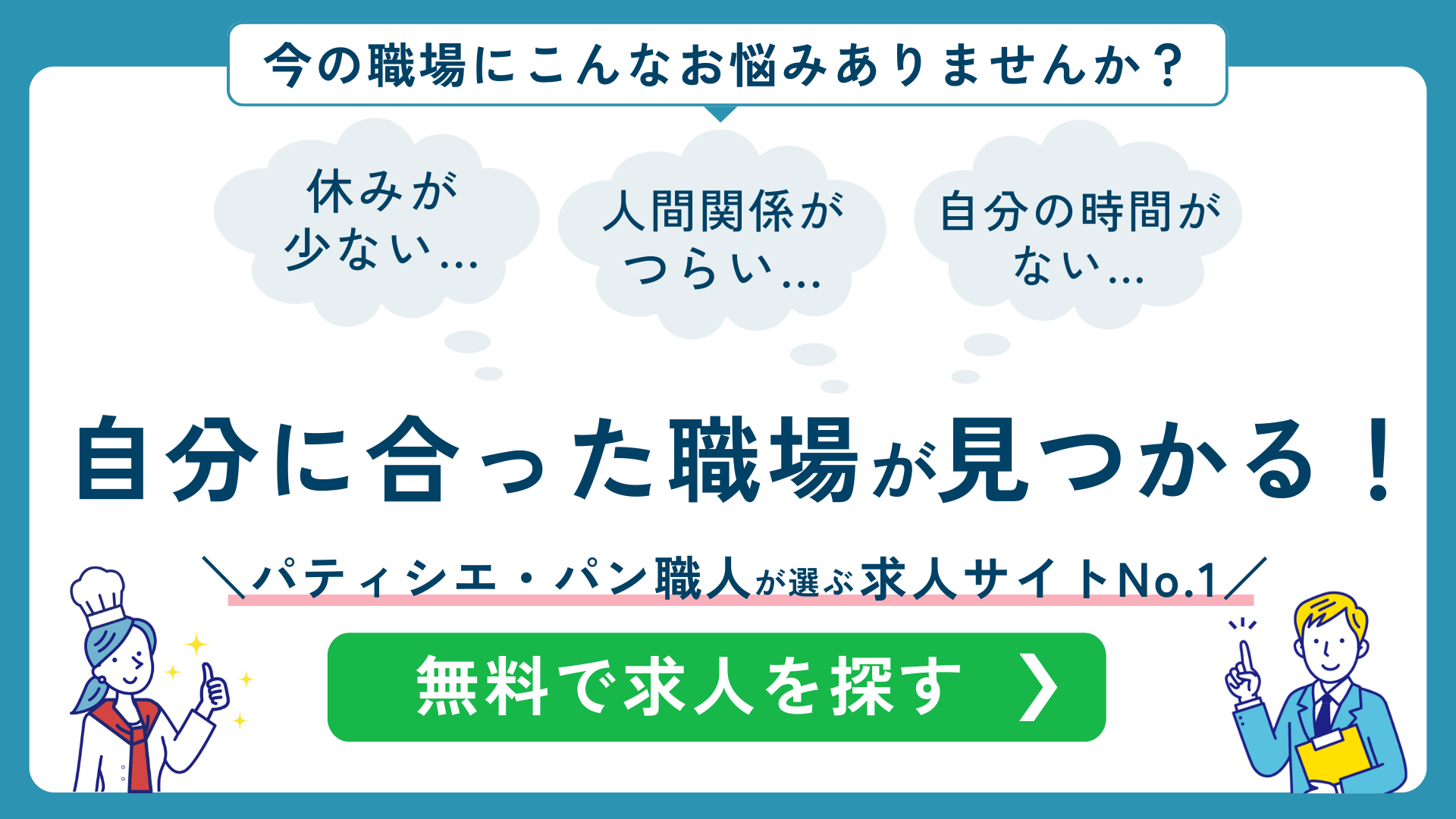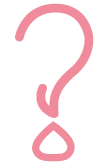
シュトーレン
カテゴリ:クリスマスの菓子

シュトーレンは、ドイツの菓子パンで、オランダではストルと呼ばれている。
クリスマスにドイツやオランダで伝統的に食べられている。正しい発音はシュトレンだが、表記はシュトーレンとされていることも多い。
生地にはレーズンやレモンピール、オレンジピール、ナッツなどが練りこまれており、焼き上がったあとに溶かしバターと染み込ませ、真っ白な粉糖をパンを覆うようにかける。その見た目から、産着に包まれた幼子イエスキリストを表しているとも言われ、クリスマスに食べられる料理のひとつとなった。
歴史
シュトーレンは、14世紀にクリスマスの贈り物としてナウムブルク(Naumburg)の当時の司教へ贈られたことから始まったと言われている。実際にシュトーレンの名前が使われるようになったのはそれから150年後のことである。シュトーレンはトンネルの形をしているところから、ドイツ語の坑道という意味にちなんでつけられたと言われている。
クリスマスの1ヶ月前のアドヴェント(待降節)の時から少しずつスライスして食べられる文化がある。日に日に熟成してパンの味が良くなるので、クリスマス当日を楽しみに待ちわびながら食べられるものである。
更新日:2018年12月11日
作成日:2018年09月12日
更新日:2018年12月11日
作成日:2018年09月12日
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの協力のもと制作されています。
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの
協力のもと制作されています。
関係項目
• レープクーヘン
レープクーヘン【独:Lebkuchen】 レープクーヘンはドイツを中心に作られているクリスマスのお菓子。 蜂蜜・香辛料、オレンジ・レモンの皮やナッツ類、チョコレートを用いて作ったものである。 ドイツではクリスマスに飾るケーキとして知られており、中に家の形をしたものがある。これらは特別に、ホイスヒェン (独:Häuschen) 、プフェッファークーヘンハウス (独:Pfefferkuchenhaus)と呼ばれている。 甘味に蜂蜜、シナモンやアニス、グローブなどのスパイスが使われていることが特徴。カルダモンやコリアンダー、ショウガ、ナツメグなどが使われることもある。 膨張剤として炭酸アンモニウム(鹿角塩)や炭酸カリウム(あるいはこの両方)などが使われる。 レープクーヘンを名乗るための基準は法律で定められており、配合のうち25%のアーモンド、もしくはほかのナッツ類が含まれていることが条件となる。 でんぷんの割合が10%以下の場合は、食料品及び日用品の品質に関する法律 (略称:LMBG)に基づいて「エリーゼンレープクーヘン」と称号される。 レープクーヘンには、最大で10%の穀粉または7.5%のデンプンを入れることができる。エリゼンレープクーヘンは、高品質ベーカリー製品に定められているため、栄養価の高いクーベルチュールのみを加えることが認められていて、栄養価の低いカカオ入りバタークリームは使ってはいけないことになっている。 歴史 レープクーヘンの名前は、「Leben(レーベン=命、生活)のKuchen(クーヘン=ケーキ)」と解釈されることが多い。Pfeffer(プフェッファー=コショウ)という意味から、スパイスを使ったケーキということで、プフェッファークーヘンとも呼ばれている。 レープクーヘンの歴史は相当古く、紀元前350年の古代エジプト時代にあった、スパイスの入った蜂蜜パンが始まりと言われている。 現在、レープクーヘンは主にクリスマスシーズンに食べられているが、かつてはイースターや他の時期にも食べられていたものである。料理の一品として、強いビールなどと一緒に食卓に出されていた。
• ビュッシュ・ド・ノエル
ビュッシュ・ド・ノエル【仏: bûche de Noël】 ビュッシュ・ド・ノエル (仏: bûche de Noël) はブッシュ・ド・ノエルとも呼ばれている。ビュッシュは木や丸太、ノエルはクリスマスを意味するところから、ビュッシュ・ド・ノエルは木の切り株の形をしたケーキで、クリスマスのケーキとして有名である。 ケーキを丸太の形に見立てるために、よくロールケーキが利用される。表面に木の色を想像させるココアクリームやバタークリームを塗り、フォークなどで引っかくことで樹皮が表現されることもある。 枝を表現するためにチョコレートを使ったり、雪を表現するために粉糖を使ってデコレーションされたりして、雪の日の木をイメージして作られる。 歴史 ビュッシュ・ド・ノエルが丸太の形をしているのについては諸説がある。 クリスマスがキリスト教より以前にあった冬至祭を起源とするのと同様、北欧の古い宗教的慣習で使われた丸太を、パリのお菓子屋がかたどって作ったもの。 もう一つには「キリストの誕生を祝い、幼い救世主を暖めて護るため、暖炉で夜通し薪を絶やさず燃やした」ことに由来し、その時の薪を表現しているとも言われている。