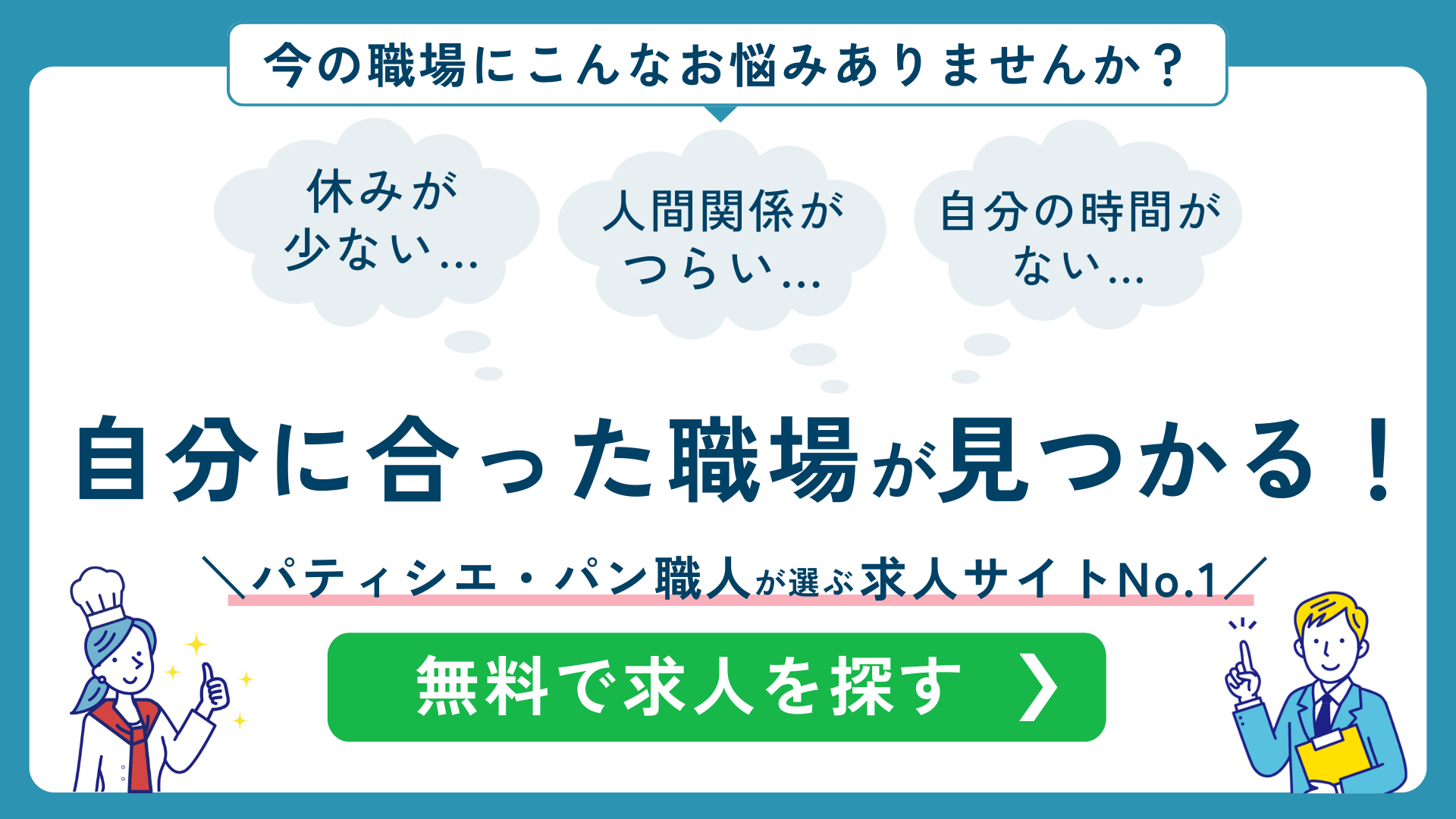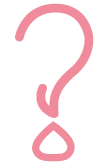
グルテン
カテゴリ:性質・現象

グルテンにはグルテニンとグリアジンという2種類のタンパク質があり、この2つが絡み合って形成される。
練れば練るほどグルテンがたくさん出てくる。家で例えるならグルテンは柱のような存在で、生地作りにおいて骨格形成の働きがある。スポンジ生地はグルテンの力で形が整い、パンはグルテンの力で膨らみ、うどんにコシが出るのもグルテンの作用である。
グルテンの量と質
小麦粉の種類によって含まれるタンパク質の量と性質が異なり、「薄力粉」「中力粉」「強力粉」の3種類にわかれている。→小麦粉の種類薄力粉は、軟質小麦を原料とする小麦粉。タンパク質の割合は小麦粉の中で一番少なく8.5%以下。粉の特徴はきめが細かく、しっとりとしていて握ると塊ができる。
強力粉は、硬質小麦を原料に作られている。タンパク質の割合が11.5%以上の小麦粉を強力粉と呼び、タンパク質の含有量が小麦粉の中で一番多い。粉の特徴はきめが粗くさらさらしていて、打ち粉に使われていたりする。
強力粉は薄力粉よりタンパク質量が多いためグルテン形成量も多く、弾力と粘り気が強い。
グルテンの作用
パン生地への影響
パンをつくる場合、小麦粉他材料と水を加えて捏ねると、軟らかく弾力がある生地になる。捏ねることでグルテンが形成され、生地を伸ばすと薄い膜のようになり、網目で細い繊維状になる。
焼成の際にオーブンで熱が加わるとイーストがガスを発生させ、膨張して体積がさらに大きくなり、よくふわふわのパンに仕上がっていく。
生地の中心温度が95~97℃に上がった際、形成されたグルテンの網目状組織は熱で変性して固くなるため、パン中にしっかりした骨組みができて冷えてもその形を保てる。でんぷんが壁、グルテンが柱の役割を果たしている。
パイ生地への影響
パイ生地は、練り合わせたり、麺棒でのばしたりした後には、必ず「生地を休ませる」という工程が入る。練り合わせたばかりの生地はグルテンにより弾性が強まり伸ばしにくくなったり、焼成の際に縮みが起こったりする。伸ばした直後のグルテンが作用したままの生地は使うことができない。生地のコシを作っているグルテンのタンパク質の粘弾性は、生地を休ませている間に変化し、ゆるまっていく。
練り合わせた生地や麺棒でのばしたばかりの生地は、グルテンの構造が無理な力で引きのばしたような状態になっている。そのため、力を加えて無理に生地をのばそうとしても、元の状態に戻ろうとする力が強く、非常にのばしにくかったり成形しにくい。
しかし、この生地を冷蔵庫でしばらく冷やして休ませるとグルテンによる弾力がだんだん弱くなり、のばしやすくなっていく。寝かしている間にグルテンの網目構造無理な力のかかっている部分が切れ、ほぐれ、構造全体に余裕ができてくるので伸ばしやすく加工しやすくなる。
グルテンに影響する副材料、添加剤
食塩はグルテンのコシを強くする性質を持っている。パン作りにおいては食塩は重要なもので、全体がしっかり締まって、弾力がありダレない。食塩を入れないと、発酵させている間に生地がダレてベタベタした仕上がりになってしまう。
食塩の量が多すぎると、パン酵母(イースト)の発酵が抑えられ、生地が膨らまなくなることもある。
サラダ油などの液状油はグルテンの無理な結合を減らしたり、グルテンと他の成分との接触をなめらかにしたりする役割がある。液状油を加えた生地は、生地全体が非常に軟らかくなり、薄く伸ばしやすい。
また、レモン汁や酢などはグルテニンとグリアジンを溶けやすくし、グルテンがやわらくなり生地が伸びやすくなる。
アルコールなどもグリアジンを溶けやすくし、グルテンを柔らかくする作用がある。
更新日:2020年04月03日
作成日:2018年09月13日
更新日:2020年04月03日
作成日:2018年09月13日
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの協力のもと制作されています。
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの
協力のもと制作されています。
関係項目
• キュアリング
発酵(キュアリング) 人間の体にとって有益となる微生物、発酵菌(善玉菌)によりでんぷんやタンパク質を分解させ、アミノ酸や糖分、アルコール分、乳酸、ビタミン類などを生成させること。発酵菌が増殖すると、別の形に変化したり、栄養分を生産することがある。 →バニラビーンズ →ヨーグルト →発酵バター →サワークリーム →ワイン 悪玉菌によってタンパク質や糖分が分解されてアンモニアや硫化水素が発生し、人体にとって有害になるものとなった場合は、発酵ではなく腐敗と呼ばれる。 イーストによる発酵 イーストとは(パンの生地発酵) イーストはパン酵母とも呼ばれる。真菌類である酵母を小麦粉や糖分に加えると、パン酵母が有する酵素がアルコール・有機酸・エステル(有機化合物)を生成し、炭酸ガスを発生させる。イーストはパンの製造にとって欠かせないものであり、酵母が発生させる炭酸ガスは膨張させてパンをふっくらと仕上げる役割がある。 発酵生地は、酵母によって生地の中で発生した炭酸ガスと、炭酸ガスを包み込むグルテンの力により膨張する。小麦粉中のグルテンの多さや、グルテンの質の良し悪しがパンの膨張を大きく左右している。 イーストが発酵するには、栄養、温度、湿度が必要になる。これらの条件がそろうと、パン生地は発酵を始める。 →イーストの種類 酵母の活動温度 酵母が活動する温度は35〜38℃、pH(水素イオン指数)4〜6(弱酸性)が最適な環境。酵母は10℃以下でほとんど活動することはなく、急冷(1分間に10℃以下)しない限り-60℃まで温度が下がっても死滅しない。逆に55℃以上に上昇した場合は、短時間で死滅してしまう。 パン生地の場合、作業性や雑菌汚染、パンの風味等を考慮すると、発酵温度は20〜38℃、pH5~5.8程度の条件下が無難な範囲といえる。生地発酵は、発酵器などに入れて行う。 パン生地の発酵 一次発酵 生地を捏ね上げたあとに行う。 発酵させることにより生地の酸化が促進され、炭酸ガスの保持力を高まり、柔軟性・伸展性のある生地ができる。炭酸ガスは生地を適度に膨張させ、発酵によって生成されたアルコールなどが蓄積されることによってパン特有の内相と食感・フレーバーが生まれる。 ベンチタイム(中間発酵) 生地の分割・丸め作業のあと、成形前に行う。 分割や丸め作業を経て作り直されたグルテンの配列を整え、若干の炭酸ガスを発生させる。また丸め作業作業などで加工硬化を起こした生地の組織を緩め、成形での作業性を良くすると共に、生地の表面がなめらかになる。 ホイロ(最終発酵) 焼成前に行う。 生地を成形した際に崩れた生地の構造を整えて柔軟性を取り戻させて炭酸ガスを発生させ、グルテンが伸びやすい状態に戻す。
• 小麦粉
世界で栽培される小麦は、栽培の季節によって春小麦と冬小麦にわかれる。 小麦は粒の色の違いで赤小麦と白小麦に分けられ、さらに粒の硬さによって硬質小麦、中間質小麦、軟質小麦に分けらる。 分けられた小麦をいろいろと組み合わせ、小麦を挽き、胚乳の部分を粉にしたものが小麦粉である。 全粒から果皮や胚芽の部分はふすま(皮くず)として除去し、胚乳の部分のみを挽いたもの。全粒100kgから、おおよそ75kgの小麦粉が得られる。 同じ小麦の胚乳部分でも、中心部は灰分が少なくなっている。中心部分の方が白く、たんぱく質の量も少なくなる。 主にこの中心部分からとれるものは上級粉といわれ、灰分が低く、乳白色または淡黄色の冴えた色をしている。表皮近くからとれる下級粉は、たんぱく質が多くなって、色がくすみ茶褐色を帯びてくる。 →灰分と小麦粉の等級 →小麦粉の種類 小麦粉の性質 小麦粉は水を加えて練り合わせると「グルテン」というタンパク質が網目状に変質して、つきたてのモチのような「粘弾性」をもつ物質に変わる。 このグルテンはお菓子作りでは欠かせないもので、生地の骨格を形成する非常に重要な役割をもっている。 でんぷんに熱を加えるとのり状になり、その状態を糊化(α化ともいう) 米に水を加え、加熱して炊飯すると粘りが出るのと同じ現象である。 糊化した物が乾燥したものを老化という。老化した状態はもとには戻らない。 炊きあがった米を出しっぱなしにして固くなったものは水を加えてもとに戻らないのと同じであり、老化した小麦粉の状態が元に戻ることはない。 ケーキ作りにおいて、スポンジ生地などのパサつきの原因になったり、しっとりしたりする原因にはこの糊化、老化の作用も大きく関係している。