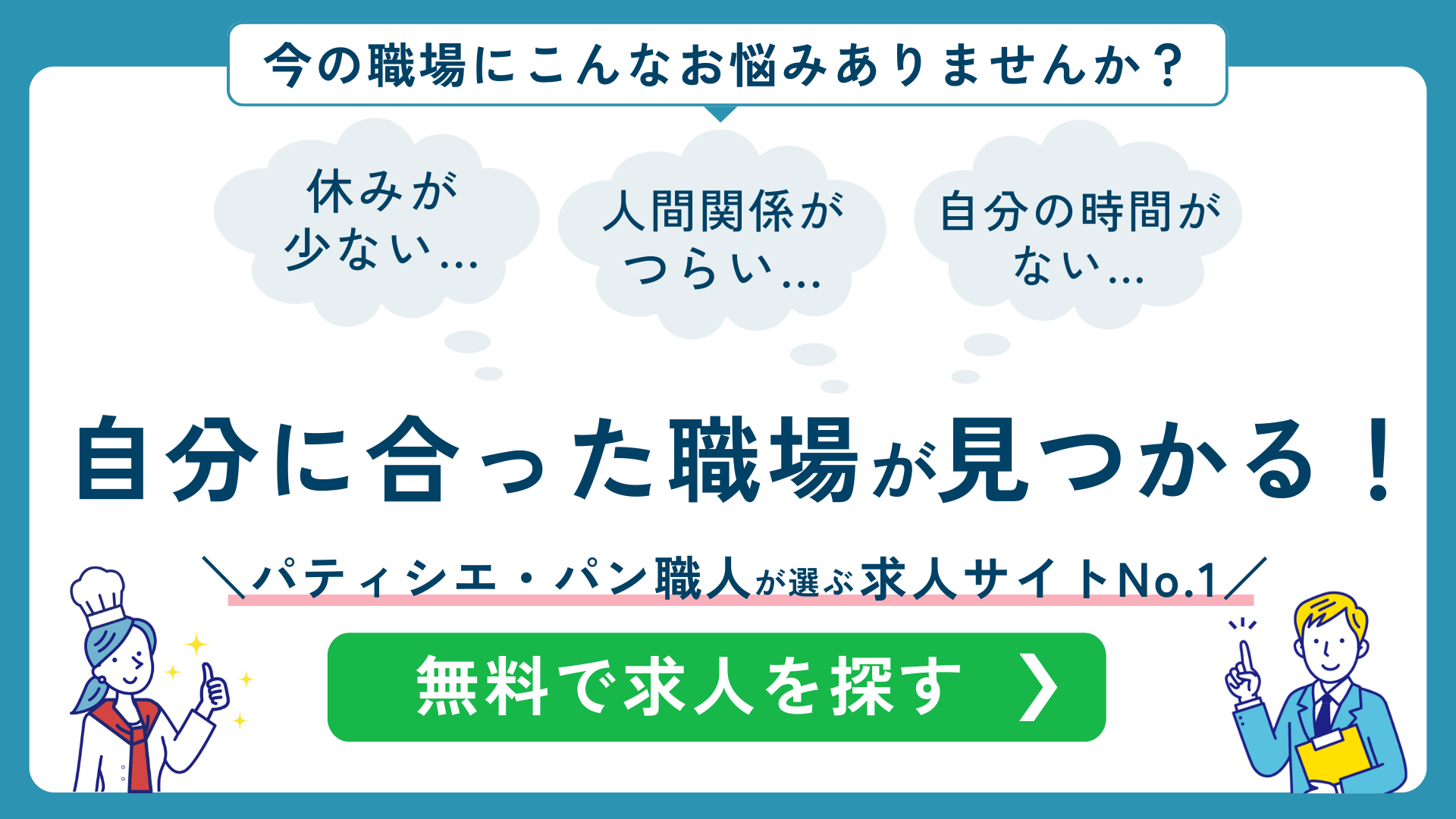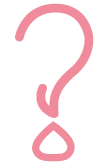
カラメリゼ
カテゴリ:仕上げる

カラメリゼとは、砂糖または砂糖に水を加えたものを煮詰め焦がしたり、直接焼き鏝やバーナーで焼いたりして、砂糖を独特の苦みと香りのある褐色物質に変えること。
砂糖に熱を加えキャラメル化させる工程が総じて『カラメリゼ』と呼ばれる。
一般的に製菓業界では、シブースト・ポムの表面や、クレーム・ブリュレの表面などに砂糖をふり、鏝やバーナーで焦がすときの事をカラメリゼと表現することが多い。
また、シブースト・ポムに使うリンゴや、タルト・タタンのリンゴを調理するときに「キャラメル」を作り、リンゴとからめることも「カラメリゼ」と表現される。
カラメリゼの種類
カラメリゼにはいろいろな方法と使い方がある。1.クリームの表面を焼き、カラメリゼする
シブーストやガトーサンマルク、ピュイ・ダムールなどのように、クリームの表面にグラニュー糖、粉糖をまぶして、焼き鏝やカラメライザーで表面を焼きカラメリゼする。カラメリゼすることにより、ケーキに独特の風味を与えるだけでなく、パリパリとした食感が生まれてベースとのコントラストが生み出される。
カラメリゼされた表面は、つやのある焦げ茶色になり、カラメリゼの回数が多いと固く厚みが出てくる。
焼きごて(カラメライザー)は十分に熱し、ケーキの表面を滑るように動かして使う。
ブリュレの場合は表面に砂糖をふり、ガスバーナーで表面をカラメリゼすることが多い。
2.砂糖、砂糖水(シロップ)を煮詰め、ソースやクリームに使う
砂糖、砂糖水(シロップ)は煮詰めると茶色のカラメルに変化する。このカラメルは煮詰め方により、カスタードプリンのソースや、ケーキのクリーム等に加えキャラメル風味のクリームとして使われたり、サントノーレやピエス・モンテなどのようにシュー生地のコーティングにも使われたりする。
熱した砂糖は、150℃以上から茶色くなる。
カラメルが好みの色になるように鍋の底にぬれ布をあてたり、ほんの少し水を加えたりしながら温度を調節する。加熱をやめてもしばらくは熱が広がっていくため、仕上げたい色になる前に温度調節するのがポイント。
3.果物やナッツ類の風味つけに使う
2と同じ手順でフライパンでカラメルを作り、リンゴやナッツを加え絡めていく。クルミ、アーモンドなどの場合は、鍋で水と砂糖を煮詰め、ナッツ類を加えよくかき混ぜる。
天板に移し、窯で時々混ぜながら焼く。
カラメリゼは、焦がし方が足りないと、香ばしさに欠けたぼんやりした味わいになる。逆に焦がしすぎると、苦味だけが強くなりすぎてお菓子の美味しさが失われてしまう。
総じて砂糖の焦がし具合の見極めと、温度調整が大事な作業である。
更新日:2018年12月11日
作成日:2018年09月13日
更新日:2018年12月11日
作成日:2018年09月13日
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの協力のもと制作されています。
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの
協力のもと制作されています。
関係項目
• メイラード反応
アミノーカルボニル(メイラード)反応とは、食品に含まれている「アミノ化合物」と「還元糖」を加熱または合わせて保存することにより、結合・分解・酸化などの複雑な反応を繰り返して、茶褐色の物質「メラノイジン」ができる現象をいう。 ケーキのスポンジやタルト、パイ、シュー、クッキー生地などを焼成したときの「焼き色」がアミノーカルボニル(メイラード)反応によりできたもの。 材料の小麦粉・バター・卵・砂糖に含まれるタンパク質やアミノ酸などの「アミノ化合物」と、糖分に含まれる「還元糖」が加熱(160℃以上)されることにより、アミノーカルボニル(メイラード)反応がおこり、茶褐色の物質「メラノイジン」ができて、焼き色になる。 また、アミノーカルボニル(メイラード)反応は色が変化するだけでなく、アミノ酸の種類と加熱温度により特有の香気成分も生成される。 スポンジやタルト生地などを焼いた時の芳ばしい香りも、アミノーカルボニル(メイラード)反応によるもの。 アミノーカルボニル(メイラード)反応の仕組みは、まだ解明されていない部分が多いが、主要素である「アミノ化合物」と「還元糖」が多いほど反応を起こしやすくなる。 グラニュー糖より上白糖のほうが焼き色を付きやすいのは、上白糖には「還元糖」が多く含まれており、アミノーカルボニル(メイラード)反応を起こしやすいため。
• クレーム・ブリュレ
クレーム・ブリュレ(仏:Crème brûlée) プリンより濃厚なアパレイユを湯せん焼きし、表面にカソナードを散らしてバーナーや焼きごてで表面を焦がしたお菓子。 ブリュレはフランス語で焦がす・焦げたという意味で、訳すと焦がしたクリームになる。 卵や牛乳、砂糖、バニラの他に生クリームが入るのでコクと滑らかさがあり、炙ってカラメル化表面にナイフを入れるとパリンと割れるのが特徴的。 歴史 クレーム・ブリュレは著名な料理人、ジョエル・ロブションが広めたとされているが、その原形はスペイン・カタロニアのお菓子、クレーム・カタラーナではないかといわれている。 カタラーナはシナモンの香りをつけたカスタードクリームのようなものに、クレーム・ブリュレと同じく表面にカソナードを散らして表面を焦がしたもので、キャラメルとクリームとの食感のコントラストが楽しめる。このお菓子が現在のクレーム・ブリュレに近しいものである。 日本で流行したのは1990年代前半ごろで、現在はパティスリーやカフェ、レストランなど幅広い場所で見られるようになった。 表面を炙ったカラメルは時間が経つにつれ溶けてしまうため、注文を受けてから表面を焼くお店も多い。