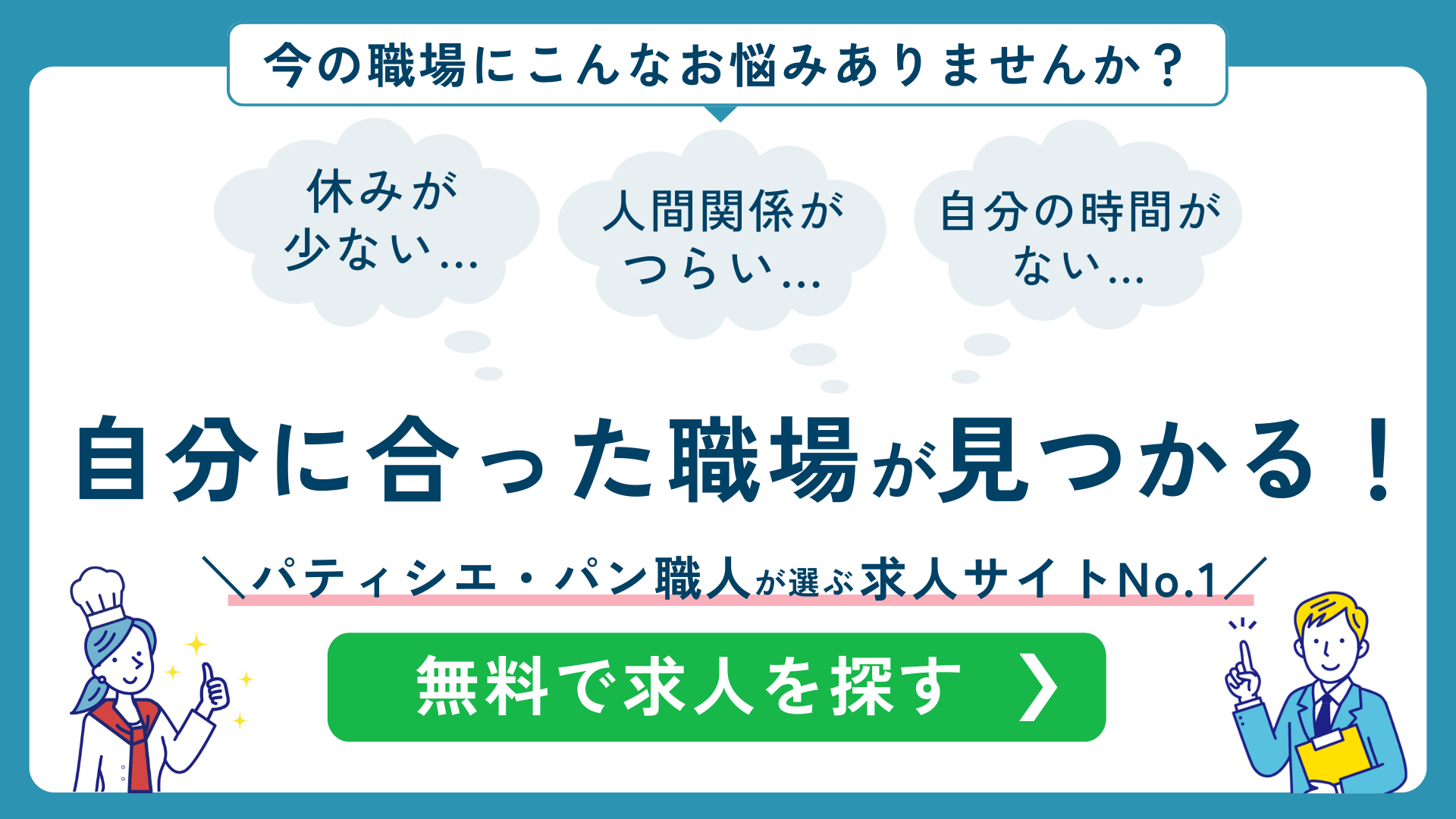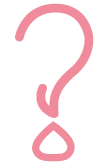
アーモンド
カテゴリ:ナッツ類

アーモンドは、バラ科サクラ属の落葉高木、またはそこから採った種実のことをいう。別名ヘントウ(扁桃)、あめんどう、ハタンキョウ(巴旦杏)とも呼ばれる。アメリカ合衆国がもっとも最大の生産地である。日本でも小豆島を始めいくつかの場所で栽培されている。
アメリカ産アーモンドの旬は8月中旬〜10月、日本産のアーモンドは梅雨時期だが、一年中流通している。
アーモンドの果実は、皮、果肉、核、仁で作られているが、通常食用しているのは『仁』の部分で果肉は食べない。仁を乾燥させて生アーモンドといい、それを炒ったり(ロースト)、揚げたりしたものが市場に並んでいる。
アーモンドの種類
アーモンドにはたくさんの種類があるが、一般的なものは長さ3cmぐらいの種子の形をしていて、香ばしい味がする。食用として主流なのがスイートアーモンド(甘扁桃仁)で、カリフォルニア産は、100%これにあたる。一方、野生種であるビターアーモンド(苦扁桃仁)はエッセンスやオイルの原料として用いられる。
ビターアーモンドに含まれるアミグダリンから分解されるベンズアルデヒドが香料の主成分となる。しかし、アミグダリンは一定量以上摂取すると有毒となるため、ビターアーモンドは食品として日本に輸入することができない。
アーモンドを粉末にしたアーモンドパウダー(アーモンドプードル)は、フィナンシェやマカロン、アマレッティ、ヌガー、マジパンなどの洋菓子に使われる。
過剰摂取による健康被害
アーモンドは健康によいとされる食品ではあるが、高カロリーのため、食べすぎは肥満につながる。また、食物繊維も過剰摂取となり、腹痛や便通異常を引き起こす恐れがある。中にはアーモンドのアルギニンという成分で口唇ヘルペスを起こす人もいる。そして、たくさん摂取することで体内に蓄積する脂溶性のビタミンE過多による病気を発症する場合もある。更新日:2018年12月11日
作成日:2018年09月07日
更新日:2018年12月11日
作成日:2018年09月07日
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの協力のもと制作されています。
パティシエWikiは現場で働くパティシエのみなさんの
協力のもと制作されています。
関係項目
• ヘーゼルナッツ
ヘーゼルナッツ【英:Hazelnuts(ヘーゼルナッツ)、仏:Noisette(ノワゼット)】 別名「西洋ハシバミ」といい、カバノキ科ハシバミ属の落葉低木の果実である。中央アジアで主に栽培されていて、その中でも特にトルコが主要産地として有名で、世界に流通するヘーゼルナッツの75%を占めている。日本で使われているヘーゼルナッツの95%はトルコ産である。ナッツ類の中でも、世界中で親しまれる代表的な種類のひとつ。 ヘーゼルナッツの旬は9月ごろで、春に花をつけて、夏の終わりから秋にかけて果実が熟す。外見はドングリに似ているが、ドングリよりも大きい。丸型や尖形、細長いものなどもある。ヘーゼルナッツの色はヘーゼル色、はしばみ色といわれていて、淡い褐色をしている。味にくせがある。 ヘーゼルナッツはナッツそのものを食べられるより、製菓や調理に使われることが多い。ヘーゼルナッツの代表的なお菓子に、チョコレートと混ぜ合わせて作る「ジャンドゥーヤ」や種実をカラメリゼした「プラリネ」がある。ヘーゼルナッツのペーストを使った「ヌテラ」は、ココア入りヘーゼルナッツスプレッドとして世界各国で販売されている。ヘーゼルナッツの風味をいかした「ヘーゼルナッツ・リキュール」も、製菓材料として重宝されている。
• くるみ
くるみ【英: Walnut、Black walnut、仏:noix、学名:Juglans)】 クルミ科クルミ属の落葉高木とその種子を加工したナッツをいう。くるみは英語ではウォールナットというが、日本ではくるみの木材のことをウォールナットという。 くるみの収穫は8月末に始まり11月末まで続く。日本では1年の通じて手に入れることができる。日本でも昔から全国の山や野に自生し、食用とされてきた。日本では長野県や東北地方などで栽培されているが、生産量が多いのはアメリカのカルフォルニアが有名である。 くるみは人間の脳に似た形をして、殻の表面にたくさんのしわが入っている。殻はとても固く、くるみ割りというくるみを割る器具で割る。くるみ割り人形はくるみを割るために作られた人形である。殻の中には実が詰まっているが、これらの実もひだがついたような独特な形となっている。 くるみは生で食べるとやや柔らかく甘い味がする。ローストしてから調理されたり、食べられるたりすることも多い。ローストすると香ばしくなり、ナッツらしいカリっとした食感になる。ローストしたくるみは製菓材料として販売されており、ケーキの飾りはもちろん、ブラウニーなどの焼き菓子にも使われる。 保存方法 殻付きのくるみは、日陰においておくだけで数か月は保つので、使うときまで殻をむかないほうがよい。むき身のものでも、しっかりと密封して、冷蔵、もしくは冷凍保存することで1年は保存することができる。また、においを吸収しやすいため、ほかの食品と一緒に置くとにおい移りすることがある。