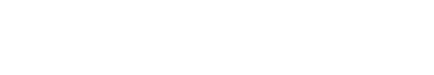この記事の目次
女性パティシエのライフイベント
結婚・妊娠・出産・育児を仕事とどう両立する?
パティシエの仕事は不規則で体力も必要ですが、最近は企業側の支援も増えています。女性パティシエ特有の悩みや将来設計
女性パティシエならではの悩みには、次のようなものがあります。- シフト制や体力仕事が多い:立ち仕事が中心で、仕込みや焼き作業など熱い機材を扱うシーンや重いものを運ぶことも多い。
- 長時間労働や不規則な勤務形態:お店の営業時間や繁忙期に合わせて勤務するため、生活リズムが不規則になりがち。
- 育児や家庭との時間確保が難しい:夫や家族との予定が合わず、保育園の送迎家事や分担も負担になりやすい。
結婚・出産後も続けるためのポイント
職場でのコミュニケーション
結婚や妊娠がわかったら、早めに上司や同僚に相談し、体調面で不安に感じていることや、業務内容で配慮が必要なものがあれば伝えておくのがおすすめです。パティシエの仕事はチームワークが命。自分だけで気にせず、周囲と慎重に情報を共有しましょう。上司・同僚への理解促進と協力体制の構築
妊娠・出産前段階から、「産休・育休をいつ頃取得するか」「復帰はどのタイミングになりそうか」目安を伝えておくと、職場も人員配置やシフト計画を立てやすくなります。健康管理と職場環境
お店の厨房は暑いことが多いので、汗をかいたあとに身体が急に冷えてしまう可能性もあります。 妊娠中は特に身体を冷やさないよう注意が必要です。休憩をこまめに取り、体調が悪いときは無理をしないようにしましょう。パティシエが知っておきたい産休・育休制度の基礎

産休・育休制度の概要
産休・育休は、働く女性が安心して出産・育児をするための国の制度です。条件を満たせば誰でも利用できます。
産前産後休暇について
女性産後休暇(産休)は、法律により定められている休暇制度で、妊娠・出産を控えたことが心身を休めるために取得できます。具体的には、出産予定日の6週間前(双子など多胎妊娠の場合は14週間前)から取得できる「産前休業」と、出産後8週間まで取得できる「産後休業」に分かれます。- 産前休業 予定日の6週間前から取得が可能です(多胎妊娠の場合は14週間前)。 妊娠後期は体調が不安定になることも多いため、早めに産前休業を利用して休養に専念することで、出産に備えることができます。
- 産後休業 出産後8週間は、原則として働けない期間と法律で定められています。
育児休業(育休)について
子どもが1歳になるまで、原則として取得することができます。 保育園に入れなかった場合ややむを得ない場合は、2歳まで延長が認められるケースも。男性の育休取得率も上がってきており、両親がともに育児休業を取得する場合、原則子が1歳までの休業可能期間が、子が1歳2か月に達するまで(2か月分はパパ(ママ)のプラス分)に延長される「パパ・ママ育休プラス」という制度もあります。パパ・ママ育休プラス制度の詳細はこちら 出典:厚生労働省「パパ・ママ育休プラス」
ポイント:育休を取得するには、必ず休業開始予定日の1ヶ月前までに企業へ申請してください。 産後休業から続けて育休に入る場合は、産前休業前もしくは産前休業中に申請しましょう。取得条件と期間、給付金の支給条件
-
条件と期間
育休は、1年以上取得していることなどの条件をクリアしていれば、正社員だけでなく契約社員や派遣社員でも妊娠中の女性であれば誰でも取得できます。 - 産休・育休中に支給される手当の内容
- 出産手当金:産休期間中に健康保険から支給される手当です。出産前42日(6週間)+出産後56日(8週間)の期間を合計した日数が基本的な支給対象期間になります。
- 出産育児一時金: 赤ちゃん一人につき通常50万円が支給されます。産院への直接支払い制度を利用すれば、分娩・入院費の負担が大幅に軽減されます。
- 育児休業給付金:育児休業期間中に雇用保険から支給されます。給与のおよそ67%(支給開始から6か月間程度)、その後は50%程度が認められます。支給条件には雇用保険への加入期間などがあるため、事前に確認が必要です。
パティシエの仕事環境で押さえておきたいポイント
- 勤務形態(早朝勤務や深夜作業など)の調整 労働基準法では、妊娠中の女性および産後1年を経過していない女性を「妊産婦」と定義し、その間妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることはできません。
- 復帰後の仕事内容や時短勤務の可能性 育休から復帰する際、時短勤務(1日6時間や実働時間短縮)制度がある会社なら、子どもが保育園に通いやすい時間帯に合わせて働けます。パティシエの場合、販売担当や仕込み担当など、比較的時間の融通が利きやすいポジションを検討してもらえることも。
児童手当・その他給付金の種類と制度の活用法
児童手当の支給条件と金額
- 対象年齢と所得制限
- 支給額はどれぐらい?
その他自治体独自の子育て支援策・給付金
住んでいる自治体によって、保育料の補助制度や一時保育サービスの利用料補助、医療費助成などが独自に設定されていることがあります。 また、「子育て支援施設」や「地域子育て支援センター」といった無料の場所で、育児相談や子どもの遊び場を提供している場合もあります。申請手続きの流れと注意点
申請期間の確認と遅れないためのチェックリスト- 出産手当金や出産育児一時金の申請期限を把握する
- 児童手当の申請は子どもが生まれたら早めに
- 自治体独自の給付金は、申請期間が短いものもあるため注意
- 健康保険証や雇用保険被保険者証、母子手帳などをご用意しています
- 勤務先の総務部・人事部、自治体の役所、ハローワークなど、提出先を間違えないようにチェック
仕事と家庭の両立に役立つライフプランニング
結婚・妊娠前から始める貯蓄計画
- 予想外の出費が発生することも… 出産にかかる費用やベビー用品の購入費、病院の入院費など、一度に大きな出費が発生することがあります。出産育児一時金は大きな助けになりますが、場合によっては持ち出しが必要になることもあります。
- 育児費用の計算をしてみる おむつ代、ミルク代、ベビーカーやチャイルドシートなど、育児には意外とお金がかかります。保育園に通う場合の保育料も確認しましょう。自治体によっては品目によって購入費用を支援してくれる制度があるため、ホームページでチェックしてみましょう!
育児とキャリアを両立するための働き方
出産後もパティシエとして働き続けたい方は、次のような働き方もありますよ。- 時短勤務やパート勤務 一日6時間程度の時短勤務で働くことができれば、保育園への送り迎えや家事との両立がしやすくなります。 一度会社に相談してみましょう。
- 在宅ワークやオンラインを活用する パティシエの仕事は実際に手を動かす作業が多いですが、最近はSNSやネット販売で自作のスイーツを販売する人も増えています。また、自宅でお菓子教室を開き、オンラインでレッスンを行うという選択肢も。
- シフト調整や夜勤・早朝勤務の軽減策 繁忙期にはどうしても早朝から準備をしたり、夜遅くまで残業が発生することがあるでしょう。小学校入学までの子を養育する労働者が請求することにより、1か月24時間、1年 150時間を超える時間外労働を制限できます。 出典:厚生労働省「Ⅶ 時間外労働の制限 Ⅶ-1 育児を行う労働者の時間外労働の制限1 (第17条第1項) 」
家族と職場と連携して続けるスケジュール管理のコツ
- パートナーや家族のサポート確保 出産後は、夫や両親など身近な家族のサポートを受けやすいように、事前に決めましょう。
- 職場の同僚・上司とのコミュニケーション 「急に子どもが熱を出して、どうしても休みたい」といったことも起きやすいのが育児期間です。 普段からチーム全体でフォローし合える関係を維持して安心です。
制度利用の際に気をつけたいこと

事前に確認しておくべき書類や準備事項
- 健康保険証や母子手帳の準備 病院役所での手続きで必要になります。産休に入る前に会社に健康保険証の番号などを確認し、母子手帳を早めにお渡ししてあげましょう。
- 雇用保険被保険者証や給与明細のコピー 育児休業給付金を申請するには、雇用保険の加入が前提となる場合が多いです。
- 勤務先の制度をチェックしてみましょう 大手企業や有名ホテル系列のパティスリーでは、独自の育児支援制度がある場合も。その場合、会社の規定を確認して最大限活用できるようにしましょう。
復帰時期のタイミングの重要性
- 保育園の空き状況 育休を1年間取得しても、復帰しようとする月に保育園がいっぱいで入れないケースもあります。 保育園の申し込みは自治体によって受付時期が決まっているため、早めに確認しておく必要があります。
- 復帰後の職場ポジションや働き方 復帰時期がわからないと、会社も人員配置を決められません。保育園の入所の目処がたったら速やかに報告しましょう。
復帰後の仕事と育児をスムーズにするポイント
- 仕事の分担やスケジュール調整 復帰してすぐにフルタイムで働くのは容易なことではありません。フルタイムで復帰するのが難しい場合には、時短勤務などを活用し、徐々に慣れていくのがおすすめです。
- ワークライフバランスを広く続けるコツ 育児と仕事の両立で疲れたときは、周囲に頼ることをためらわないでください。 赤ちゃんを数時間だけ預かってもらい、自分の時間を確保することも大切です。
まとめ:給付金を賢く活用して理想のワークライフを実現しよう
今日からできるアクションリスト
各種手当や制度の申請手続きの確認- 自身が受けられる可能性のある給付金(産休・育休、児童手当、自治体の補助など)をリストアップ
- 申請先と申請期限をメモ
- 産休・育休中にどれだけ手当が入るか計算
- 育児に必要な出費を概算する
- 「いつ出産予定か」「どれくらい休むのか」「復帰時期はいつごろを想定しているか」を共有
- 妊娠前後の体調変化や育児について理解してもらう
ライフステージの変化に合わせたキャリア選択
- ライフステージの変化を前提にプランを考える 「20代後半で出産」「30代で子育てしながらキャリアアップ」といった長期的な視点でキャリアを描くと、将来の仕事選びがしやすくなります。
- 家族との時間を大切にしながら仕事も充実させる秘訣 夫や両親と家事・育児を分担し、職場の仲間と協力しながら仕事を続けられる環境づくりを心がけましょう。